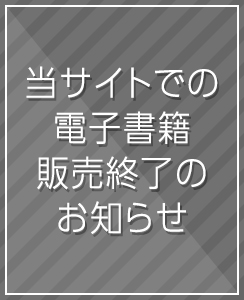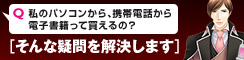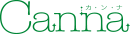男ふたり夜ふかしごはん
食わんと寝られへん。いただきます!
芦屋の古い一軒家で暮らす眼科医の遠峯と、転がり込んできた後輩で小説家の白石。
時々喧嘩もするけれど、男ふたりの同居生活は気安くて快適だ。
なにより、食の好みが合うのがいい。
食卓で仕上げる、あったかポテサラ、
祖母直伝の味噌だれで食べる水餃子、
お祝いで超大人のお子様ライス、
ふわふわ卵のけいらん温麺、
懐かしのご褒美弁当、
憧れのミートボールスパゲティ
ちょっと豪華なさけ茶漬け、
身も心も温まる、蒸し寿司──
読んだらお腹が空くこと間違いなし、禁断のお夜食歳時記。
フシノ厨房の簡単レシピあり
プルドポーク、コーンスープ、味噌だれなど
つくってみよう☆
四月
他府県の人にどちらにお住まいですか、と問われて答えると、「ああ、セレブの」というリアクションを食らう確率が驚くほど高い。
それが、俺が暮らす兵庫県芦屋市という街だ。
最近では「そうでもない」といちいち言うのが嫌で、一度きりしか会わないような相手には、「神戸界隈」と曖昧に答えることも多い。
芦屋市は広大な神戸市の東側にちょんと隣接しているので、嘘ではない。
というか、「セレブの街ではない」と全面的に否定するわけにもいかないので面倒臭い、というのが正直なところだ。
確かに、市内にはいわゆる富裕層が多く暮らすエリアが厳然と存在するし、街中を走る自動車の海外車種率もけっこう高い。
関西では指折りの繁華街である大阪の梅田と神戸の三宮、その両方にアクセスがよく、電車やバスで通える距離に私立の有名校がいくつもあり、風紀を乱しうる遊戯設備がほとんど存在せず、治安がいい。
俺が人の子の親なら、我が子をここで育てたいときっと願うだろう。
でも俺は気ままなひとり者で、昔ながらの住宅街である宮塚町の、祖母が遺してくれた一軒家で暮らしている。
阪神・淡路大震災が起こったとき、神戸市内で夜勤中だった祖父は火災に巻き込まれて命を落とし、今、俺が暮らしているこの家も、半壊状態になった。
幸い、奇跡的に無傷で助かった祖母は、夫と共に長年暮らした自宅を見捨てたくなかったのだろう。いくら引っ越しを勧められても頑として断り、自宅を修繕して、五年前に死ぬまでひとりで住み続けた。
子供の頃から、俺は、祖父母と同じくらいこの家が好きだった。
それだけに祖母の死後、父や叔父叔母たちが、この家を売却してそのお金を皆で分配しようと話し合っているのを聞いて、それが最善だとわかっていながら、割って入らずにはいられなかった。
そう、俺はノスタルジーに突き動かされるまま、「自分がこの家を買い取って住む」と宣言してしまったのだ。
両親には古い家のデメリットを山ほど聞かされ、制止されたが、こういうのは典型的な、反対されればされるほどムキになる案件だ。
俺はかなり強引に「親戚価格」で家を買い取り、周囲の呆れ顔など少しも気にせず、単身、軽やかに移り住んだ。
職場であるN総合病院には、JRでも阪神電車でも一本で行き来できるのがいい。
もっとも、どちらの芦屋駅からも、我が家までは徒歩で十五分ほどかかるのだが、これは職場での運動不足を解消すべく、神様が強制的にエクササイズを課してくれたのだと考えることにしている。
今日も暮れゆく静かな通りをてくてくと歩いて我が家に戻り、玄関扉を開けるなり、漂ってきたのはトマト系のいい匂い、聞こえてきたのはやや音程の怪しい鼻歌だった。
そう、俺、遠峯朔は相変わらず独り身ではあるが、今や一人暮らしではないのだ。
「帰ったで」
「はーい、お帰りなさーい」
小さな家なので、玄関で靴を脱ぎながらそこそこの声を上げれば、家じゅうに届く。
返事もまたしかりだ。
声から十数秒遅れて玄関に顔を見せたのは、同居人の白石真生である。
高校時代、俺たちはアーチェリー部の先輩後輩だった。とはいえ、俺が三年のときに白石が一年生だったので、共に部活に励んだのはほんの半年足らずだ。
それなのに白石はやけに俺に懐いていて、卒業式では今にも泣きそうな顔で俺を見送ってくれた。
その白石が、十三年ぶりに突然やってきたのは、一昨年のことだ。
奴は、東京在住の小説家になっていた。
どうやら打たれ弱くて繊細なところは高校時代から少しも変わらなかったようで、多くは語らないものの、白石は仕事に行き詰まり、逃げ出してきたらしい。
「しばらく、先輩んちに置いてもらおうと思って!」
やはり高校時代とあまり変わらないとぼけた調子で奴にそう言われた俺は、若干考えはしたものの、しばらくなら構うまいと奴との同居を受け入れた。
それがズルズル続いて、今である。
もはや一つ屋根の下の共同生活も三年目に突入し、目の前でニヤニヤ……いや、おそらく本人的にはニコニコしている男の存在にもすっかり慣れてしまった。
今となっては、一人暮らしだった頃の生活がどんなだったか思い出すのが難しいほどだ。
「どうかしました?」
不思議そうに首を傾げる白石の呑気そうな顔を見上げ、俺は「いんや」と首を振り、玄関に上がった。
「ええ匂いやな。晩飯、何や?」
白石は、ニコニコして両手を腰に当てた。
ここに来たときからずっと愛用している高校時代の芋ジャーの上から、エプロンを着けるというお馴染みの姿だ。
「それは出してのお楽しみ。先に風呂入るでしょ?」
いつからか、白石は、俺が帰宅する頃合いを見計らって、風呂に湯を張ってくれるようになった。
病院で長時間過ごすので、帰ったらすぐ風呂で全身を洗い流したいのは確かなのだが、そんな新妻めいたことをしなくてもいいとだいぶ前に言ったら、白石は「正直、先輩のためってわけでもないんですよ」と恥ずかしそうに頭を掻いた。
小説家という仕事の特性上、油断すると何時間も座りっぱなしになりがちの白石は、洗濯機を回すとか、炊飯器をセットするとか、浴槽に湯を張るとか、そういう家事のルーティンを作ることで、身体を動かすチャンスを得ているらしい。
なるほどと納得して、以来、帰宅して即、風呂に飛び込めるありがたみを満喫しているというわけだ。
「風呂、二十分で上がるわ」
俺がそう言うと、白石はストレートな迷惑顔をした。
「僕、まだ仕事中なので、もっとゆっくりしてくださいよ。そうだな、四十分後とか?」
「わかった。ほな、のんびり湯に浸かって、美顔パックでもしよか」
「マジすか。意識高いな!」
「嘘やっちゅうねん」
「なーんだ。先輩、無駄にお肌キレイだから、冗談に聞こえないですよ」
「んなアホな」
意外と真顔でツッコミを入れてくる白石に軽く手を振って、俺は二階の寝室へ行った。
八畳の洋間だが、二畳分はこぢんまりしたウォークインクローゼットになっているので、使える面積は限られている。
ベッドと本棚とライティングデスクを置くと、余剰のスペースは大して残されていない。
ショルダーバッグをデスクの上に、ジャケットとネクタイはベッドの上にバサリと置いて、俺は階下の浴室へ向かった。
亡き祖母はとにかく植物が好きな人で、生前は脱衣所どころか、浴室の窓際にも、おそらくは湿度を好むタイプであろう植物の鉢が置かれていたものだ。
申し訳ないことに、引き継いだ俺が放置したせいでことごとく枯らしてしまったのだが、一鉢だけ小さなサボテンが生き残り、今も脱衣所の細長い窓の枠にちょこんと存在し続けている。
相変わらず俺は少しも構っていないが、おそらく白石が世話してくれているのだろう。気付けば、ゴルフボール大のサボテン本体から、小指の先ほどのピンク色の蕾が飛び出している。
「お前、花なんか咲かせるんかいな」
当たり前のことにけっこう本気で驚きつつ、俺は脱いだワイシャツを洗濯機にバサリと放り込んだ。
入浴を済ませた俺が、きっかり四十分後にダイニングキッチンに行ってみると、白石は、ちょうどノートパソコンの電源を落としているところだった。
「お、時間ぴったりですね」
「几帳面やからな。古典的な京都しぐさやったら、五分遅れてくるんが礼儀なんかもしれんけど」
「それは都市伝説じゃないんですか?」
「どやろ」
そんなくだらない会話をしながら、俺は白石が執筆道具を片付けた後のテーブルに、ランチョンマットを向かい合わせに二枚置いた。
それから冷蔵庫を開け、ビールを一缶だけ取り出して、白石に訊ねる。
「一杯飲むか?」
俺は、特に酒好きというわけではない。だが、よく働いた一日の終わりに、小さなグラス一杯の軽いアルコールでみずからを労ってやるのは、そう悪いことではないと思っている。
ただ、白石は深夜がいちばん執筆がはかどる時間帯らしく、たいていの日は、朝方までこのダイニングテーブルで仕事を続けている。
だから、このタイミングで酒を飲みたいかどうか、いつも訊ねるようにしているのだ。
「ん、そうですね。ちょっと飲もうかな」
「よっしゃ。ほな」
俺は、缶ビールとグラスを二つ、テーブルに運んだ。それからまた、キッチンに引き返す。
「箸でええか?」
「あー、フォークとナイフもお願いします。スプーンもあったほうがいいかも」
「お、今夜は洋食か」
「どっちかっていうと、そうですね」
曖昧な返事をして、白石はガスの火を弱める。
「あ、先輩、ついでにシチュー皿も出しといてください」
「あいよ」
俺は言われたとおり、ランチョンマットの上にカトラリーをセットして、真っ白なシチュー皿を二枚、取り出した。
食器のほとんどは亡き祖母が使っていたもので、これもそうだ。
幼い頃、このホテルのレストランを思わせる皿で祖母ご自慢のビーフシチューを出され、あたためたロールパンを添えてもらうと、何だか王侯貴族になったような気分で嬉しかったものだ。
「この皿、昔っから好きやねん」
そう言うと、両手にオーブンミトンをはめ、楕円形の鋳物鍋を持った白石は、「へえ」と、ちょっと不思議そうな顔をした。
テーブルの真ん中に、オレンジ色の鋳物鍋を据え、その隣にポテトサラダのボウルを置いて、炊きたての飯をよそえば、夕食の支度は完了だ。
俺たちは、いつものように差し向かいで、食事を始めた。
最初に俺が二人分のグラスにビールを注ぎ、互いにグラスを軽く掲げるだけの乾杯をする。
「先輩は、今日も一日、お疲れ様でした!」
「おう、お前も半日、お疲れさん。あとの半日も頑張れや」
「はーい」
お決まりのやり取りでビールを一口飲み、グラスを置いた白石は、ボウルを俺のほうに軽く押しやった。
「そんじゃ先輩は、ポテサラの仕上げをお願いします。僕、おかずをよそいますから」
「おう」
俺は大きめのガラスボウルを引き寄せ、片手でしっかりホールドすると、もう一方の手に竹製のへらを持ち、中身を慎重に混ぜ始めた。
最近、白石がよく作る、テーブルで仕上げるタイプの温かなポテトサラダだ。
ボウルの中には、レンジで蒸かして皮を剥いたばかりのあつあつのジャガイモが三つ、半熟と固ゆでの間くらいの絶妙な茹で加減の卵が二つ、そこにみじん切りのタマネギ、カリカリに炒めたベーコン、コロコロに刻んだ胡瓜、それに今夜は、先日のお好み焼きに使った残りのイカ天を手で小さく割ったものと、生姜の甘酢漬けの細切りが入っている。
そうした雑多な具材を木べらで粗く潰しながらマヨネーズと共にざっくり混ぜ合わせ、仕上げに粗挽きの黒胡椒を振れば完成だ。
あまり料理をしない俺にも、ここまでお膳立てしてもらえば、それなりに上首尾な仕上げができようというものだ。
俺がポテトサラダを二つの小鉢に盛り分けているあいだに、白石は鋳物鍋の蓋を開け、出来上がった料理をレードルでシチュー皿にたっぷりよそってくれた。
夕食の主菜は、ロールキャベツだった。
なるほど、帰宅したときに俺の鼻が嗅ぎつけたトマト臭は、ロールキャベツのソースの香りだったのか。
いつもより小さなサイズにきっちり巻かれたロールキャベツが、盛大に湯気を立てるトマトソースの中に、なんだか気持ちよさそうに浸っている。
わざと大ぶりに切って一緒に煮込んだタマネギと人参、それに何故かいつもロールキャベツと同居しているふた口サイズのソーセージも、実に旨そうだ。
「さて、準備オッケーですね。召し上がれ!」
「おう、いただきます。今日もありがとうさん」
俺は軽く頭を下げて挨拶すると、さっそくナイフとフォークを取った。
「高級洋食みたいやな」
「高級洋食って、僕のイメージでは、資生堂パーラーとかですけど」
「そやそや、そういう奴や」
俺がそう言うと、白石はポテトサラダを食べようとした手を止めて、照れ笑いした。
「行ったことないですけど、たぶんそりゃ褒めすぎでしょ」
「そんなことはあれへん。まあ、二割くらいは、この皿の効果やけどな!」
「それでも、八割は僕の料理の手柄ですか。やー、褒められちゃったな」
へへへ、と笑って、白石はポテトサラダを大きな口で頬張る。
俺は白い皿と赤いトマトソースのコントラストを楽しみながら、ロールキャベツにナイフを入れた。
キャベツは驚くほど柔らかく煮えていて、ナイフが吸い込まれるように沈んでいく。きちんと巻いた形を保っているのが不思議なくらいだ。
「やらかいな!」
俺の感嘆の声に、白石は、にかっと顔中で笑った。今度は、ストレートに得意げだ。
「でっしょー! 仕事しながら、ことこと気長に煮込みましたからね」
「そやろな」
俺はうなずきつつ、大きめの一口をよく吹き冷ましてから、頬張ってみた。
「む」
思わず、声が出た。
よく、テレビに出ている芸能人が、何を食べても「とろける~」と口走るのを、俺はこれまで苦々しい思いで見ていた。
そんなに瞬時にとろける食べ物があってたまるか。そう思っていたのだ。
しかし、今、口の中にあるロールキャベツは、まさにその「とろける」系と言ってもいいのではなかろうか。
噛みしめるまでもなく、何層かあるはずのキャベツは儚くほどけ、中に詰まっていた挽き肉とタマネギみじん切りを合わせたものも、たっぷりの肉汁を放出しつつ呆気なくバラバラになっていく。
まさに、全員、速やかに現地解散……という趣だ。
名前も忘れた芸能人たちよ、すまなかった。とろける食べ物は、確かに実在した。
「とろっとろや。旨い」
「よかった。まだ肌寒いですから、煮込み料理が旨いっすよね」
「旨い。夜は冷えるから、熱々が何よりのご馳走やな。そやけど」
俺はあっという間にロールキャベツを二つ平らげ、三つ目に手をつける前に、鍋越しに白石の顔を見た。
「大丈夫なんか、お前」
「はい?」
白石も、ロールキャベツの味を確かめつつ、キョトンとした顔で視線を上げる。
「何がです?」
「何がて、えらい手の込んだ晩飯やないか。もしかして、仕事が上手いこといってへんの違うんか」
「んがぐぐ」
某長寿番組のキャラクターのような声を上げた白石は、わざわざカトラリーを置き、両手で心臓のあたりを押さえてみせた。
どうやら、図星だったらしい。
俺は、途端に心配になって、自分もフォークとナイフを置いた。
「また小説の仕事、アカンことになっとんのか」
我ながら深刻な声が出てしまって、俺は苦笑いした。
高校生の頃から、白石にはやけに図太いところと繊細なところが同居していて、おそらく小説の仕事は、繊細な部分のほうを主に使ってやっているのだろう。
この家に来てからも、たまに〆切間際にスランプに陥って、夢遊病のハイジのように家の中をうろついている姿を見かけたことがある。
そもそも東京を逃げ出した理由も、仕事に行き詰まり、将来どころか現状への不安から精神的に不安定になったせいなので、先輩として俺が心配性になるのも無理からぬことだろう。
当の白石は、微妙な困り顔で、肉付きの薄い肩をヒョイと竦めた。
「大当たりです。今日、なんかこう、手が止まっちゃってて。なんでわかっちゃったかなあ」
「わからんわけがないやろ。お前がやたらとチマチマ手ぇかかる料理を作り出したら、仕事で行き詰まったと相場が決まっとう」
「うう、ですよね。僕、そういうとこわかりやすいんですよ」
白石がシュンと項垂れたので、俺は慌ててフォローを試みる。
「まあ、俺はいつも以上に旨いもん食えるからありがたい限りやけど、大丈夫なんか?」
「うーん、どうでしょう」
「どうでしょうて、アイデアが干上がってしもて、話が作られへんとかか?」
すると白石は、力なく首を横に振った。
「いえ、話は作れます。実際、プロットは通ってるんですよ」
「プロット……つまり、あらすじは完成しとると」
「そうそう」
何だかよくわからなくて、俺は首を捻った。
「それやったら、あとはそのあらすじに沿って書いたらええだけ違うんか」
誓って悪気はなかったのだが、その発言は、どうやら作家にはとんだ地雷だったらしい。白石は珍しく本気の膨れっ面になり、両手で軽くはあるがやたら素速くタカタカとテーブルを叩いた。
「あああ、もう! 素人はすぐにそういうこと言うー!」
「素人て」
「そういや、素人ってことはないか。先輩だって、論文とか書くでしょ?」
「今はさほど書かんけど、学位を取らなあかんかった頃は、もりもり書いたな」
「じゃあ、わかるんじゃないですか? 読み物は、ツカミが最重要なんだって」
「ツカミて」
「論文には、ツカミってないんですか?」
俺は左右に首を倒しながら考え考え答えた。
「ツカミっちゅうか、まあ、Abstract、つまり論文の要旨やな。それを、論文のいちばん最初んとこに置くねん」
「つまり、あらすじ?」
「そうやな。まあ、タイトルと要旨で、どういう論文かっちゅうことをわかるように書かんならん。めっちゃようけ投稿論文が来る学術誌なんかやったら、まずはタイトルと要旨でざっとふるいに掛けるっちゅう話も聞いたことがあるくらいや」
「じゃあ、めっちゃ大事なツカミじゃないですか」
白石は不機嫌をひとまず脇に措き、興味をそそられた様子で身を乗り出す。だが俺は、力なく首を振った。
「いやあ、まあ、大事っちゃ大事やし、ツカミっちゃツカミやけど、小説とは重要視されることが違うと思うで」
「そうなんですか? こう、物語のカラーを即座に理解してもらえるようなキャッチーな言葉とか、気持ちを乗せやすい導入とか……」
「は、要らん。論文の要旨に必要とされるんは、明快さと簡潔さ、ほんで内容を正確に反映させることやな」
白石は大袈裟な顰めっ面で腕組みする。
「んんん、確かに方向性が違うかも」
「せやろ。論文やったら、研究がある程度まとまった時点で、何について、どんなデータを挙げて、どういう結論にたどり着くかはもう決まっとるわけやから、それをただ正確にまとめていけばええだけやな。いちばんの悩みどころは英文法やって言うてもええくらいや」
「あ、英語なんだ」
「日本語の論文も書くけど、やっぱしこう、ちゃんとした論文は世界的な学術雑誌に送らなあかんからな。インパクトファクター言うて、わかりやすう言うたら学術雑誌のミシュラン評価みたいなもんがあるねん」
「へー!」
「それの高い雑誌に掲載されたほうが、ええ評価をゲットできるっちゅうわけや」
「はー、なるほどぉ。世の中には、その道に入り込んでいかないとわかんないことが、いっぱいあるなあ」
感心しきりでそう言ったあと、白石は再びカトラリーを手にしてこう打ち明けた。
「僕のほうは、書き出しで詰まってるんですよ」
俺も、せっかくの料理が冷めないうちにと、今度はポテトサラダの小鉢に手を伸ばした。自分が仕上げたので完全なる手前味噌だが、混ぜ具合が敢えてざっくりなので、一口ごとに味が違うのが楽しい。
「書き出し……『トンネルを抜けるとどこそこでした』とかいうアレか。それこそ、キャッチーさがものを言いそうな奴やな」
「そうそう。読者さんは、書き出しをまず読んで、続きを読むかどうか判断するわけですから、すっげー大事なパートなんですよ、書き出しって」
「そやな。俺はあんまし読書家やないけど、それでもたまに、出オチみたいな小説に出くわすもんな。なんや、おもろいのは序盤だけやないか、と思うたときにはもう買うてしもてるわけやし」
「そうそう、それ。勿論、そんな風なガッカリは絶対させたくないですけど、でもまあ、それくらい書き出しって重要だし、難しいんです」
「で、そのええ書き出しがまだ思い浮かばんっちゅうわけか」
白石は、またしょんぼりした顔で頷く。
「そうなんですよね。作品のキーになるような言葉をしょっぱなにバーンと出すか、あるいは主人公のモノローグから始めるか……。間違っても、舞台の説明から始めないようにしないと」
意外な言葉に、俺はポテトサラダの最後の一口を頬張ってから訊ねた。
「なんでや? こういう舞台で話書きますっちゅう説明、大事やろ」
「そうですけど、いきなり延々と解説されたら、学校の授業みたいで退屈でしょ?」
「そやろか」
「いや、腕の立つ作家さんなら、そういう文章ですら面白くできるんでしょうけど、僕は平凡なもの書きですからね。やっぱそこは冒険しないでおこうと思います」
「へえ。ほんで、作品のキーになるような言葉は」
「見つかってません、まだ」
「そら大変や」
「大変なんですよ~。最初に特別な一言からアイデアが広がることもあるんですけど、今回はそういうのじゃないから。でも、見つけなきゃ。いや、こういうの考えながら食事をしちゃうと美味しくなくなるから、あとでひとりで呻きながら頑張りますよ」
「お、おう」
「それよか、ポテサラの仕上げは先輩にお願いするに限りますね。このいい加減な混ぜっぷりが、結果オーライっていうか」
「適当て言うな。ええ塩梅て言うんや、こういうんは」
「えー」
クスクス笑う白石にホッとしつつ、俺はロールキャベツの強力な伏兵、見るからに旨そうに煮えたソーセージを、フォークでザクリと突き刺した……。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細