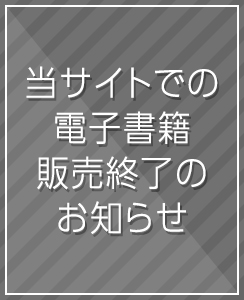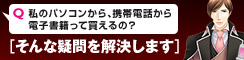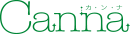REDRUM
悦んでいる自分の身体が恨めしい──
妻が殺され、息子の光希を心の支えにする雅人。
けれどやがて、拘束され嬲られて達する忌まわしくも淫らな夢を見るようになる。
目覚めると生々しい名残があり、それが現実だと思い知らされた。
監視されているのか、見計らったように電話が鳴り屈辱的な指示を与えられる。
光希を人質にとられたに等しい雅人は、拒めない。
追い詰められ、ずっと傍にいてくれる友人の貴之に縋るが──。
「なんなの? 叩かれて、見られて感じてるの? 本当にどうしようもない淫乱だな。節操なさすぎ」
言葉とともに定規がバチンッと、雅人の高く掲げた尻を打ち据える。
「んっ、ぐっつ……」
思わず喘いだ。
痺れるような甘い痛みが全身を蕩かせてゆき、雅人の官能に引火する。意識が正常に保てなくなってきて、くらくらする。
「痛いの? でも、叩かれるたびに、ここ大きくなってるけど? 後ろの孔も物欲しげにひくひくさせて、ほんといやらしいね」
男は定規の先で、鈴口からぽとぽとと涎を垂らしている雅人の反り返った花芯をつんつんと突いた。
「はああっ、んっ、ぐうっ」
叩かれた痛みで、より敏感になっていた雅人は、それだけでたわいなく蜜を迸らせた。
こんな得体の知れない男に嬲られ辱められて、その上容易く快楽に導かれて。
自分のはしたなさに雅人は、ただただ恥ずかしくて消えてしまいたい、と思うのに、身体は男の残酷な仕打ちを、もっともっとと欲しがって強欲だ。
「本当に驚くよ。叩かれて、こんなに悦ぶなんて」
基也が冷ややかに嘲る。
本当にそうだ。こんな男にいたぶられて、こんなに感じてしまって。雅人は自分の身体が恨めしかった。けれども、目と口を塞がれ、四肢を拘束されていては逃げることも叶わない。
「そんな変態の雅人には、いいものをあげる」
男の言葉に、今度はなにをされるのかと身を竦め怯える。
と、細い金属の筒のようなモノが雅人の秘孔に宛がわれた。
「これ、なんだかわかる?」
嬉しそうな声が尋ねる。秘孔にぴたりと当てられた冷たくて硬い感触──。
これは……。
雅人の頭から血の気が引いていく。
エアガン? そう答えを出すと、ふるふると身体が震えて治まらない。
股間を閉じてしまいたいのに、左右に大きく割り開かれた脚はどんなに力を込めて動かしてもびくともしない。
「そんなに怖がることないよ。こいつがとても気持ちよくしてくれるよ」
くくっと男が笑う。
それはまるで楽しい遊びを見つけた子どものようだった。
そうだ、基也とはそういう男だ。いつまでも姉のすねにかじりついて、いい年をして、まったく大人になろうという意志のない……。
乱暴に肉襞を押し広げ、冷たい感触とともにぐいっと筒口が雅人の窄まりに押し当てられた。
「ひっ!」
思わず悲鳴を上げて腰を引きかけた。しかし、男は雅人の腰を掴むと、筒口をぐりぐりと左右に捻って奥へと突っ込んでいく。抜き差しし、ごりりと前立腺のしこりを擦り上げるたび、冷たい金属がしだいに奇妙な熱を雅人の身体に熾していく。
「んんっ、ふ……っ、う、う……」
恐怖に震えていたはずの雅人の口から、種類の違う呻き声が漏れはじめた。
「ほらっ、やっぱり好きなんじゃないか。お上品ぶってもダメだよ」
またしても男は、くくっと笑う。
「んん……っ、くっ、ふ……っ」
雅人はたまらず腰を揺さぶる。男は雅人の口から猿ぐつわを外した。
「ねえ、好きなら好きって言おうか。正直に言わないと引き金引くよ」
「す、好きです。とても……ああっ」
自由になった口に、空気を吸い込むと、雅人はよがった。
気を失いそうなほどの陶酔感が雅人の全身を包み込む。
殺されるかもしれないという恐怖は、甘やかな毒のように快楽を増幅していた。
男のエアガンの動きに合わせて、雅人は激しく腰をくねらせる。
やがて視界に広がる闇が、真っ白な光に熔け落ちていく。
快感の波が、ひときわ大きくなって雅人のすべてを飲み尽くしていく。
飲み込まれた雅人は、ただ力なくくずおれる。
男の機械的な笑い声が、しだいに意識から遠のいて聞こえなくなった。
目が覚めた時、雅人はきちんとパジャマを着て、乱れて濡れたシーツに身体を横たえていた。外はまだ薄暗かったが、悪夢のような夜は明けていた。
夢だと思いたかった。
けれど、手首についた赤い痣や、まだ腫れの引かない臀部の痛みが、夢なんかじゃない、現実に起こったことなのだと雅人に教えていた。
なによりも身体の奥に残る、この凍るような恐怖と熱く痺れる快感の余韻。
気持ちとはうらはらな、自分のあさましい肉体が忌々しくて眉を顰める。
いったい誰がこの家に入り込んで、あんな屈辱的なことをするのだろう。
寝室には南向きに窓があったが、いつもきちんとロックされている。
雅人は、アイボリーのハイネックセーターとジーンズをチェストから取り出し着替えると、階下に降りていった。
玄関、テラス、勝手口、果ては大の大人がとうてい出入りできそうもないトイレやバスルームのちいさな窓まで、鍵がかかっていることを確かめてまわった。けれども、どこにも鍵の外れたところはなかった。どうやって家の中に入ることができたのだろう。
そういえば警察で亜矢の所持品を確認した時、携帯や財布とともにキーケースがなくなっていた。
もし犯人が持ち去っていたなら、この家に自由に出入りできるはずだ。そう思い至ると、雅人は携帯に手を伸ばした。まだ六時三十分だ。光希を起こす前に、警察にこのことを言おう。
と、突然、着信音が鳴った。発信番号を見て、あっと息を飲む。
亜矢、と表示された画面を震える指先で触れる。
「はい……?」
恐る恐る雅人は電話に出た。
『やあ、おはよう。昨夜は随分楽しんだみたいだね』
くくくっ、と受話器の向こうから笑い声がした。くらりと目眩がした。
それは紛れもなく、昨夜雅人を打ちのめし、いたぶった男の声だった。
『今、警察に電話しようとしただろ?』
雅人は大きく目を瞠った。
見られている? 今、この瞬間も?
テラスの窓から外を見る。庭の木々がやっと射してきた朝陽に、影を落としている。もしかしてあの木立の後ろに潜んでいるのだろうか?
心臓の鼓動がバクバクと激しくなる。
『くくっ、探しても無駄だよ』
耳障りな雑音混じりの、機械的な笑い声。
膝がガクガクと震えて、雅人はその場にうずくまった。
『いいか。警察には言うな。そんなことをしたら、お前のかわいい息子がどうなっても知らないぞ』
男はそれだけ言うと電話を切った。
「あ、待って。お願い、光希には手を出さないで!」
雅人の悲鳴は、しかし男には届かなかった。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細