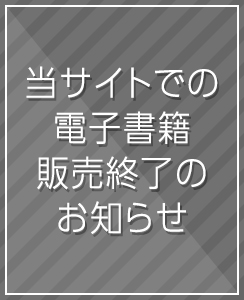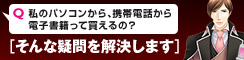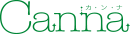性悪狐は夜に啼く
書籍紹介
もっと、撫でさせてやってもいいぞ
復讐に燃える化け狐の秋野は、怪我で蹲っていた所を建設会社の若社長・北斗に拾われた。仇とライバルだという彼を利用し復讐を遂げようとするが、北斗のおおらか過ぎる言動に振り回される。どんなに高飛車な態度で我儘をしても、「最高に可愛い」と撫で回してきて、動揺のあまり耳と尻尾が出てしまう始末。その上、世話をさせてやっている北斗の温もりが心地良くなってきて……。
立ち読み
声が止められない。簡単すぎるほど簡単に理性が消え失せそうになる。ただ、そこに触れられるだけで。
「……耳」
ふと、北斗が呟いた。耳がどうしたと、秋野は無意識に逸らしていた顔を相手に向けた。北斗の姿が水底にいるみたいに揺らいでいる。秋野の瞳が潤んでいるせいだ。
「本当に、あんた、あの狐なんだな」
深く感動したように呟きながら、北斗が秋野の頭に触れる。こめかみの辺りに触れられてやっと秋野は気付く。完璧に人の姿になっていたはずなのに、耳が、狐のものに戻ってしまっている。
北斗に触れられ、こそばゆくて、その耳が震えた。
「ぴるぴる動いてる。すげぇな」
妙な擬音を口にしながら、北斗がしつこく秋野の耳を撫でた。秋野は嫌がって首を振る。くすぐったい。動くたびに、ベッドに擦れた背中の傷が痛む。
ずきずきと疼くようなのに、それすら快楽に繋がっていくこの感覚が、秋野は昔から大嫌いなのに、どうしても抗えない。
「ん──痛むか?」
しきりに体を動かしている様子に気付いた北斗が、秋野の腰を掴んでそっと身を起こさせる。
そのまま、秋野は向かいに座った北斗に凭れるようにして抱き寄せられた。
「この姿の時の方が痛々しいな。人間の病院に連れていって、よくなるもんか?」
北斗は秋野の狐の耳に唇をつけながら、剥き出しの背中を、傷口に触れないよう注意しているのがわかる仕種で撫でてくる。秋野は触れられた背筋や耳をぞくぞくと震わせながら、自ら北斗の方に身を寄せる動きになってしまった。
「無駄……だ、人の、医者なんて……」
「そっか。何かそんな気がしてたんだよな」
北斗の手は秋野の背筋を下りていき、腰の辺りに触れた。
「……しっぽ」
笑いを含んだ声で囁かれるまでもなく秋野にも自覚があった。耳のみならず、尾も、狐のものが戻ってしまっている。さっきから勝手に左右に振れて、秋野自身の肌をその毛並みが撫でていた。
口惜しくて吐き気がしそうだ。これではどう見たって、北斗に触れられることに悦びを感じているという反応だ。
堪えようとしても、北斗は容赦なく耳の中に舌まで入れてくるし、尻尾のつけ根から先まで撫でたり、割れた尾の間を執拗に指で擦ってくるし、秋野の体が悦ぶことを最初から熟知しているような愛撫をやめない。
何なんだこいつは一体、と繰り返し内心で悪態をつきながらも、秋野は北斗に身を寄せるようにしながら、罵声の代わりに甘い声を繰り返し漏らし続ける。
「あ……ん、ぁ……っ、……やめろ……嫌だ……」
「そうかそうか、嫌か」
どうにか制止しようと訴えてみても、これだ。笑いを含んだ声で、宥めるような、からかうような調子で言いながら、北斗はますますしつこく秋野の耳や尻尾を撫で回すばかりだった。
腹立ちに任せて、秋野は北斗の肩に噛みついた。一瞬北斗が驚いたように身を揺らしたが、すっかり体から力の抜けている秋野は相手の肉、いや皮膚すら牙で貫くことができず、それは単なる甘噛みになった。北斗が震えたのだって、痛みのせいではなく、多分、快感のせいだ。
「ん……? そんな、気持ちいいか?」
「……ぅ……」
ふざけるな、と唸り声を上げているつもりなのに、鼻に掛かったような甘えた喘ぎ声になる。
名前と痣で縛ったかつての主を殺して逃れて以来、秋野が自分の意志以外で誰かに体を許したことはなかった。
(なのに、どうして……っ)
北斗は秋野の髪を撫で耳に鼻や唇や舌で触れ、背中や尾に触れ、その手を、今度は腰から腹の方に動かした。
体を押しつけているのだから、秋野がすっかり発情していることに北斗はもう気付いているだろう。だからあたりまえの仕種で、秋野の性器にまで触れてきた。
「あぁ……っ」
また遠慮のない仕種で触れられ、秋野は大きく体を震わせる。
「すごいな。こんなに感じやすいのか」
北斗の言葉はいちいち感に堪えないといった響きで、それが秋野の苛立ちと羞恥を煽る。口惜しい。腹立たしい。人の手でこんなに乱されるなんて。
いっそ、もう狐の姿に戻ってやろうかと思った。傷は痛むし、体に触れられて興奮させられているおかげで、体力が消耗してしまう。人の姿でいるのは疲れるから、狐に戻れば、北斗だってさすがに獣に不埒な行為をする気は失せるだろうし──、
(いや)
そう考えてから、秋野は自分の予測を否定した。
(こいつは、狐の姿でだって、止めないんじゃないのか)
北斗の吐息も熱っぽくなっている。秋野に触れて、乱れる姿に、興奮している。しかも耳や尻尾にしつこくしつこく、それはもうしつこく触れている。
狐に戻ってもこんなふうに体を弄られると思うと抵抗感が湧いて出て、秋野は相手の手で尾と性器とを同時に撫でられ、擦られ、身も心も高められながら、必死になって人間の姿を保った。
◇◇◇
いかされたのは一度だけだったが、それでもう、秋野は疲労困憊して、ベッドにぐったりと俯せになった。
「殺すぞ……殺してやる……」
呻くようにそう繰り返す。
北斗はそんな秋野の恨み言には答えず、湯で濡らした温かいタオルで体を拭いたり、水差しで(半ば強引に、口の端に飲み口を突っ込んで)水を飲ませたりと、甲斐甲斐しかった。
北斗がひどく上機嫌なのが伝わってくる。髪を撫でられ、収められない尻尾を撫でられ、また耳にキスをされ、しかし一方的に射精させられたあとは心身の昂ぶりが収まった秋野にとっては、触れられることがただただ煩わしいばかりだ。
「本当に、綺麗な毛並みだよな。見た目より柔らかいし。狐の時の方がもっと柔らかいか」
北斗が秋野の髪をブラシで梳いている。背中と肩の傷にはガーゼが当てられていた。秋野がじっとしているのは、疲れたせいと、その傷がいい加減痛すぎるせいだ。
「あんたは綺麗なものの塊みたいな奴だな。肌も瞳も綺麗だ。好みとしちゃ、もうちょっとふっくらしてる方がいい気もするけど」
「……おまえの好みなんか知るか」
「声もいい。唸ってるのも、何だか可愛いし」
無意識に唸り声を上げていた秋野は、そう言われて喉を震わせるのをやめた。
「こうまで好みを絵に描いたようなのに出会えるなんて、俺はよっぽど日頃の行いがいいんだろうな。せっかくの縁だ、俺はあんたに何だってしてやる。俺は俺のものに、少しだって不自由はさせない」
この男はもしかしたら頭がおかしいんじゃないかと、本格的に秋野は疑った。
「だから、誰がおまえのものだ。俺は誰のものにもならない」
二度と、絶対、死んでもだ。その決意を込めて告げるのに、北斗はてんで取り合わず、ひたすら、愛おしそうに秋野の髪の手入れをするばかりだ。
あまりに明け透けに好意を寄せられ、正直なところを言えば、秋野は少し毒気を抜かれていた。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細