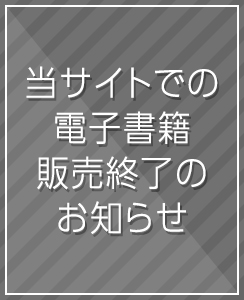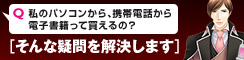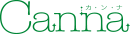執事候補生・七号
書籍紹介
主人に絶対服従。それがアカデミーのルールだ。
その全寮制の執事養成学校では、薬物が蔓延し人身売買が行われているという。新人警察官の悠の任務は、潜入している捜査員に渡す解毒薬を学校へ持ち込むという、簡単なものだった。しかし悠は学校から脱出できず、執事候補生として薬を打たれてしまう。候補生達に屈辱的な仕打ちをしては愉しむ主人達。反発した悠は学長に躾けと称して嬲られ、恍惚の中で専属を誓わされて……。
立ち読み
「七号、皆様お待ちかねのようだ。そろそろ、おまえの服従を見せてやれ。おまえは、誰のものだ?」
───そんなこと、言えるわけがない……!
憎しみの籠もったまなざしで振り返ろうとした悠の尻に、学長の平手が飛んだ。
「ひゃ、あ……う……っ……」
ほんの小さな刺激を、叩かれた身体の中心に埋め込まれた秘密が増幅する。刺激は電撃のように広がり、悠の全身は恍惚に包まれた。
放蕩に浸ってきた男たちが息を呑み、一瞬、静寂がその場を支配する。
「あ……ああっ、う……う……うあっ……」
自分の口から漏れた嬌声だけが響いていることに気付いて悠が我に返ったのは、制服の中に白濁を放った後だった。
「七号、正気を保って、聞かれたことに答えろ」
「あっ……う……」
身を灼く羞恥で蹲った身体を、学長が立たせる。
「おまえは、誰のものだ?」
「ぼ……僕は……」
「答えなければ、もう一度、ここを打つ」
尻に置かれた学長の手から、じんわりと痺れが広がる。
───もう一度叩かれたら、また、みっともなく達してしまう……。
胸の底が冷えていくような恐怖で、身体が震えた。
「僕は、が、学長のもの……です」
「ルールは覚えているな」
「執事候補生は……ご主人様に絶対服従……」
「証をみせてやれ」
身を灼く羞恥の炎が、残酷な言葉に激しく燃え上がる。
初めての日、庭で私服を脱ぎ捨てたときのように毅然とした態度をとることは、今の悠には不可能だった。
惨めさに重く頭を垂れたまま、サスペンダーを外し制服のズボンを落とす。後ろを向いて上着をたくし上げると、凶悪な玩具の底辺が露わになった。
「プラグを入れたのか」
「高価なOMを追加で使うまでもない。反抗的な態度を矯正するなら、これとDMの投与を遅らせるだけで十分だ」
「それでここまで従順になるなら……」
「では、七号は学長と契約済みということで……」
「異存はない」
「ということだ、七号」
学長は、悠の向きを変えて観衆の方を向かせた。
「いい機会だ、三号の契約者に昨夜の無礼を詫びておけ」
学長が促す。
「どうした、正式な礼の作法なら、もう知っているはずだ。習ったばかりで、もう、忘れたか?」
悠は、足を揃え伸ばした手を膝へ滑らせ、ゆっくりと上体を倒して頭を下げた。
「……申し訳ありませ……ん……でした……」
きっちりと嵌められたプラグは、悠がじっと動かずにいれば、おとなしくしている。立っているとき、歩いているときは、違和感を頭から閉め出すこともできる。が、階段を上り下りするときははっきりと意識しなければならない。そして、ホテルサービス技能のクラスで習った通り、腰を突き出す格好になるお辞儀では、中で動き回っているのではないかと思うほど存在を主張する。
「……っ!」
身体の動きに応じて異物を押し出そうとする内壁と、抵抗するプラグの側面が擦れ合って、押し出された液体が下着にじわじわと染みるのを防げない。
───前も後ろも濡れて……る……。
悠は、真っ直ぐに保たなければならない首と背中を丸めながら、そろそろと頭を上げた。
「洗練が足りない。牧園アカデミーが送り出す執事には、一流ホテルや政治家や企業の重役の秘書に相応しいレベルが要求される。おまえの卒業は、当分先になりそうだな」
学長の批評に続いて、どっと笑いが起きる。
「学長は、自分の執事の卒業にも厳しいということか」
「しかし、たったの一晩であそこまで仕込んだ手腕には感心しましたよ」
「さぞ立派な執事に育つことだろう、楽しみだな」
契約者と杖の男が笑い合いながら庭に移動すると、遠巻きにしていた執事候補生たちが見えた。真っ赤に染まった顔を仲間に見られたくない悠は、俯いて階段の手すりに縋り、欄干に描き出された牧園家の八重桜の紋を見つめた。
「聞いた通り、七号は俺付きの執事候補生になった。今日のホテルサービスの授業には出席せずに、俺の指導を受ける。三号と五号は庭の給仕に戻れ、主人たちを待たせるな。一号は俺のブランチを部屋へ。七号の昼食もついでに用意してやれ」
指示を受けて、控えめな足音が次々に去っていく。
「四号は七号の替えの制服をすべて俺の私室に運べ」
「……はい」
四号の返事が聞こえても、悠はまだ顔を上げられなかった。
情けない姿は、アカデミーに来た直後にも見られた。
だが、ほんの少しでも、自分が学長に好意を抱いていたこと、それを知られていたことが、たまらなく恥ずかしかった。
「七号は、着替えてから俺の給仕だ」
そう言って私室に戻った学長を、のろのろと追いかける。
扉の前で追いついた四号が自分を見ても何も言わず、黙って籠を置いていってくれたのが有り難かった。
籠には、制服が二セット入っていた。はじめに着替えた日、三セットも支給されるのを不思議に思ったことを思い出す。あのとき、四号は三セットでも足りないくらいだ、と言った。自分の体液の染みたズボンを履き替えている今は、その意味がよくわかる。
おそるおそる時間をかけて着替え終えた後、いつも通り無言で食事を運んできた一号からワゴンを受け取り、学長の分を執務机に並べた。
「コーヒーを注ぐタイミングは、俺の合図の後だ」
「……はい」
悠は、コーヒーのポットを抱えて待っていたが、合図はサラダとロールパンと卵料理を食べ終わるまでなかったので、学長の食事の間、ずっと斜め後ろに立ち続けていなければならなかった。
じりじりと炙るような違和感に耐えながら、悠は、仲間たちのことを考えた。
───四号は、まだ学長を信じているんだろうか。学長が僕と契約したのも、何か理由があってのことだと考えて……。
甘い考えは、すぐに捨てた方がいい、と悠は四号に伝えたいと思った。
───学長にとっては、執事候補生のことなんてどうでもいいんだ。ただ、自分の利益のために利用しているだけだ。
それをわかってもらうには、学長にされたことを話した方がいいだろうか?
───だめだ、話せない。
見られてしまった今朝の件はともかく、昨日、暴行を受けたことはとても話せない。
───話せるわけがない、あんなこと……!
感情の高ぶりに反応してキュッと窄まった内壁が、強く異物に擦りつけられる。
「う……っ……」
ポットを持って学長の合図を待ち、学長の黒々と流れる長髪や、広い背で揺れる黒いリボンを見ていなければならない悠は、学長のことを考えないわけにいかなかった。が、考えることは、怒りや憎しみの感情を高めることになり、結果、自分を縛る枷をさらに強めてしまう。そして、その刺激は、自分にプラグを挿入した学長について、ますます考えさせることになり……。
───学長を意識すればするほどプラグの影響は強くなる……なのに、どうして僕は学長のことばかり……。
惨めさで胸が黒く塗りつぶされそうになったとき、ようやく学長がコーヒーカップを指さした。
その指が長く、男性的な美しさを備えていることが無性に悔しい。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細