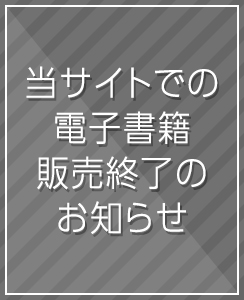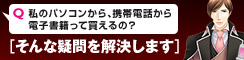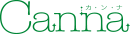白百合の供物
書籍紹介
堕ちた雄犬なら、じゃれつかせてやろう──。
軍基地を慰問した司教のヨエルは、幼馴染のリヒトと再会する。准将となっていた彼は、兄弟を亡くしながらも、ヨエルと再会を果たすためのし上がってきたという。だが、ヨエルは素直に喜べなかった。聖衣を纏ってはいるがヨエルは穢され、男を籠絡して情報を得る密偵となっていたのだ。変わらぬ思慕を向けるリヒトに言いようのない苛立ちが募り、彼を堕とそうとするが──!?
立ち読み
「……でき、ない」
長い葛藤の末、リヒトが吐き出した結論は、ヨエルが予想した通りのものだった。
「出来ない……ヨエルを告発だなんて、出来るわけがない! だってヨエルは、俺の聖者で…大切な大切な、……、で…っ」
最後の方は嗚咽のせいでよく聞き取れなかったが、どうせ大切な幼馴染とでも言ったのだろう。リヒトの頭の中にはお花畑があって、その真ん中には相変わらずヨエルが聖者然として佇んでいるらしい。
「ヨエル…、俺、絶対誰にも言わない。アイスラー閣下には後で俺が釘を刺しておく。だからヨエル、すぐにでもここを出て…」
「任務を放棄すれば、私は猊下の放った刺客に殺される。どこに逃げても無駄だ。教会の目は、大陸中どこにでもあるんだからな。…それに、絶対言わないだなんてただの口約束を、信用出来るものか」
「そんな…じゃあ、どうすれば…」
弱り果てたリヒトとは裏腹に、ヨエルは内心ほくそ笑んだ。
──この時を待っていた。
「なら、私を抱け」
「……えっ?」
「私を抱いて、私のものになれ。そうすれば信じてやる」
本当にリヒトを我が物にしたいわけではない。ただ支配して、白い花に彩られた幻想を打ち砕き、代わりに現実を突き付けてやりたいだけだ。そうすれば、自分ではどうしようもない嫉妬も、少しは和らぐかもしれない。
「…くが……、ヨエルの、ものに……?」
俯き加減の呟きは、不気味にかすれていたせいでひどく聞き取りづらかった。
ヨエルは何故か背筋が粟立つのを感じたが、リヒトがやおら顔を上げればそれもすぐに収まる。
「俺がヨエルのものになれば…、ヨエルは本当に信じてくれるのか…?」
薬が回ったせいで褐色の頬は口付けの直後よりもいっそう色付き、緑の双眸には隠し切れない欲望がちらついている。
誠実な英雄よりも、ヨエルは欲望にまみれた雄の方が遥かに信用出来た。後者なら、いくらでも身体で支配が可能だからだ。
ヨエルは紅い舌を見せ付けるように覗かせ、口の端を舐め上げた。ごくん、と喉を鳴らす男の頬を、白い指先でつつく。
「お前次第だ。……その身体で、私を信用させてみろ」
噛み付くような口付けが、挑発の答えだった。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細