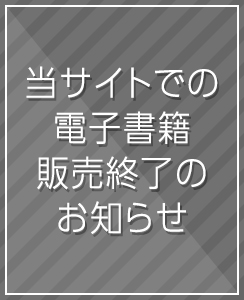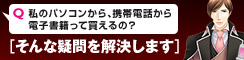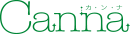男ふたりで12ヶ月おやつ
今日もおやつ箱には甘い幸せが詰まっている。
芦屋の古い一軒家で暮らす眼科医の遠峯と、そこに転がり込んだ後輩で小説家の白石。
男ふたりの同居生活は、気安くて快適だ。
白石の作る晩飯もうまい。
そして、甘党の遠峯が欠かさないおやつ──。
ほんのり温かい手作りショートブレッド
温泉帰りに炭酸煎餅
仮想彼氏が作るティラミスっぽいやつ
大人のスイーツ、コーヒーモンブラン
夏風邪には綺麗な銘菓ういろう
罪深さで美味しさ割増な裏おやつのホットケーキ
特別なデザート、クレープ・シュゼット──。
椹野先生のお気に入りがいっぱい!
男ふたりのおやつ歳時記。
先輩の家は、兵庫県芦屋市宮塚町にある。
芦屋は、オシャレなことで有名な神戸市の隣にある、いわゆるリッチ&フェイマスな人たちが住む街……だとテレビは言うし、僕も、実際に住んでみるまではそう思っていた。
確かに道を走る外車率の高さはなかなかのものだし、見るからにお金持ちそうな人たちも見かけるけれど、決してそれだけではない気がする。
少なくとも先輩と僕が暮らしている辺りは、ちょっと下町感のある、すこぶる暮らしやすい庶民的なエリアだ。
近所の人たちは、けっこう適当な服装でそのへんを歩いているし、気楽に食事ができる店や昔ながらの小さな専門店なんかも、少し歩けばたくさんある。
あと、芦屋は、地理的要素がなかなか面白い。
まず、北には六甲山、南には大阪湾があって、両者の距離は驚くほど近い。
正直、ここに来てから、方角を間違えることが一切なくなった。山が見えたらそっちが北、海が見えたらそっちが南だ。山に分け入ってしまうと話は別だろうが、街中にいる限り、この法則は決して崩れない。
おまけに、面白いくらい東西方向に向かってほぼ平行に、三本も電車が走っている。
いちばん山側が阪急電鉄、真ん中がJR、そして海側が阪神電車だ。
さらに、JRと阪神の間には国道二号線、阪神の南側には国道四十三号線が走っていて、四十三号線沿いには、阪神高速の高架道路も見える。
とにかく、自分が今いる場所を把握するのがこんなに簡単な街は、生まれて初めてだ。
おかげで、驚くほどスムーズに、僕は芦屋という街に馴染むことができた。
それに、かつて先輩のお祖母さんが暮らしていたこの小さくて古い家にも、僕はたった一年で、昔からここにいたみたいな深い愛着を抱いている。
先輩は眼科医で、電車で数駅の距離にあるN医大付属の総合病院に勤めている。
先輩がいない日中、僕は執筆の傍ら、家事もする。だから、家のことには、もはや先輩よりもずっと詳しいのだ。
別に、先輩から、家に置いてやる代わりに家事をしろと言われたわけじゃない。
後輩価格にも程がある金額だということは自覚しているものの、ちゃんと家賃だって入れている。
でも、僕は家にいる時間が長いから、自分の仕事の合間にあれこれやれる。男所帯の家事なんてそう大変ではないし、ちょくちょく身体を動かせるのもありがたい。
歩いて買い物に行くと、その道すがら、色んなものを見たり聞いたり、匂いを嗅いだりする。
そんなささやかな経験から降ってくるアイデアも少なくないのだと、この街に来てから気付いた。
そんなわけで、今の僕は、主夫兼小説家という生活を送っている。
ピーッ! ピーッ! ピーッ!
小説が書き上がった喜びに浸る間もなく、洗濯機が、仕事が終わったぞと僕を呼んだ。
「あーはいはい」
律儀に機械に返事をして、僕は立ち上がりながらマウスを操作し、書き上がったばかりの原稿にしっかりと保存をかけた。
これを怠ったばかりに悲惨な目に遭ったことがあるので、データの保存に関しては、ついナーヴァスになってしまう。
この話をしたとき、遠峯先輩は滅茶苦茶笑っていたけれど、誰が、宅配便を取りに出た一分かそこいらの間に、パソコンが煙を噴き上げるなんて想像するだろう。
どうも原因はパソコンの中に溜まった埃だったようなので、大元をただせば僕が悪い。でも、何も〆切当日の昼過ぎに、そんな大惨事にならなくてもよさそうなものだ。
とにかく、席を離れるときには必ず、データをクラウドとメモリースティックの両方に保存する。そのルールを今日も守り、僕は洗濯物を回収して庭に干すべく、ダイニングルームを離れた。
東京で暮らしていたアパートは、ベランダに洗濯物を干してはいけないルールだった。そうでなくても、交通量の多い道路が目の前にあったから、外に干したりしたら、せっかく洗った服が真っ黒になったことだろう。
だから、ここに来て、庭先に物干し竿を見つけたときには凄くビックリしたし、初めてそこに洗濯物を干したときには、昭和のお母さんになったみたいな気がした。
「うーん、いい天気だ」
洗濯物を入れた大きなバスケットを抱え、和室の縁側から、踏み石の上に置いたサンダルをつっかけて庭に降りると、柔らかな風が頬を撫でた。
春だ。
四月に入ったから当たり前といえばそうだけれど、完膚なきまでに春が来ている。
僕は物干し竿のそばにバスケットを置き、両手を広げて深呼吸した。軽くのけぞった体勢のまま、視線を空に向ける。
夏ほどきっぱりしていない、どこかふわっとした色合いの青空には、白くて小さくてこんもりした雲が、はぐれ羊みたいにところどころに浮かんでいる。
「春だなあ」
頭の中で思うだけでは飽き足らず、僕はそう呟いてみた。
声に苦い響きがあるのは、気のせいじゃない。
春なのに。
せっかく春が来たのに、僕ときたら、今年は満開の桜をミスってしまった。
さっきまで書いていた原稿が死ぬほど難航したせいで、この一週間あまり、僕はまったく外出しなかった。
屋外に出るのは、こうして洗濯物を干しに行くときや、郵便物や宅配便を受け取るときだけ。
あとはずっと、家の中で一階と二階を往復するだけの日々を過ごしていた。
先輩は不思議そうな顔をして、「座っとってもはかどらんのやったら、出掛けたらええやないか」と何度か言った。
まったくもってそのとおりだし、普段なら、気分転換を言い訳に、外へ繰り出したかもしれない。
でも、今回ばかりはそういう気持ちになれなかった。
外に出たら、街のそこここで桜が咲いていて、うららかな陽射しの中、僕はきっとお花見気分になってしまう。
担当編集さんにはジリジリした気持ちで原稿を待って貰っておきながら、僕がそんな浮ついたことをしていいはずがないのだ。
僕の原稿の上がりが遅くなったせいで、編集さんは楽しい気持ちでお花見に行けないかもしれない。僕の知らないところで、友だちや家族との大事な予定をキャンセルしているかもしれない。
そう思ったら、完成まで意地でも外に出てはいけないような気持ちになって、久々に徹底的な籠城戦を展開してしまった。
時折、庭のまだひょろりとした桜にまばらについた花を眺めたけれど、あとはほとんど……家事と、削りまくった睡眠時間、それに食事の時間以外は、ずっとノートパソコンの画面を睨んでいた。
原稿が書き上がるまで、楽しいことは何ひとつしてはいけない。
そんな、誰も望んでいない縛りを勝手に自分に掛けて、闇雲に自分を追い込んで、どうにかゴールにたどり着いた。
「一応、最後まで書けたから、まあいいんだけどさ」
ひとりごちつつ、僕は物干し竿をざっと拭いて、まずはタオル類を干し始めた。
男のふたり暮らしなので、洗濯物はそれほど出ない。洗濯機を回すのは、せいぜい週に二、三度くらいだ。
(やっぱり、惜しいことをしたな)
バスタオルを物干し竿に引っかけ、裾を揃えてパンパンと皺を伸ばしながら、心の中で呟く。
先輩には「桜は来年また見ればいいですけど、原稿がちゃんと書けないと、来年の今頃は無職になってるかもしれないですから」と言ったし、それは本当だ。
でも、立て続けの災害や異常気象を見ると、毎年、桜がちゃんと咲き、僕らが無事にそれを楽しむことができるとは限らないんじゃないだろうか。
ああ、何だかとても残念な、虚しい気持ちになってきた。
せっかく原稿が仕上がって解放的な気分になりかけていたのに、この大きすぎる「やらかした感」は何なんだ。
いくら悔やんでも、もう今年の桜は終了してしまったんだから仕方がない。
前向きにいこう。来年は、ちゃんとお花見ができるスケジュールで働こう。
気持ちを切り替えようと思ったけれど、なかなか上手くいかない。
せっかくの陽気なのに、僕はどこか塞いだ気持ちのまま洗濯物を干し終え、スゴスゴと家に入ったのだった。
「うーん、チェックは、もうちょっと時間を置いてからやりたいし、打ち出しだけしておこうかな」
僕は、自分の部屋から小さなプリンターを持ってきて、ダイニングテーブルの上に置いた。用紙をセットして、さっき書き上げたばかりの原稿を印刷し始める。
このプリンターは、こちらへ来てから、JR大阪駅近くの家電量販店で買ったものだ。
先輩は、僕がダイニングテーブルで仕事をすることについては何とも思っていないようだけれど、食事をする場所に、仕事道具をあれもこれもと持ち込むのは気が引ける。
ほぼ毎日使うノートパソコン以外のものは、二階の自分の部屋からその都度持ってくることにしているのだ。
かーこん、かーこん、と独特の音を立ててのんびり一枚ずつ印刷してくれるプリンターの仕事ぶりを横目に見ながら、僕はテーブルのあちこちに広げた資料を片付け、一山に積み直した。
それから、一息入れようと、間続きのキッチンでお茶を煎れた。
遠峯先輩は、飲食物にさほどこだわらないといつも言う。でも僕から見れば、物凄く限局的にこだわる人だし、結構なグルメでもある。
どうでもいいものについては本気でどうでもいいらしいけれど、これでなくては、というものについては、わざわざ取り寄せてまで家に置く。
お茶もその一つだ。
僕はどんなご庶民ティーでも気にしないほうなのに、先輩ときたら、お茶はたいていルピシアのオンラインストアで調達して、キッチンに常備している。そのくせ、急須やティーポットを使うのは面倒らしく、すべてがティーバッグだ。
僕も洗い物が減るので、そのほうがありがたい。
先輩が「何でも好きに飲み食いせえよ」と言ってくれるので、僕はまるで我が物のように緑茶を選び、電気ケトルで沸かした熱湯を注いだ。
お茶好きの人に見られたら、「適温まで湯を冷ませ」と怒られるかもしれない。
でも、ルピシアのティーバッグの袋には、「熱湯でも、少し冷ましたお湯でも、水出しでも、どんないれ方でもおいしく入ります」とわざわざ書いてあるので、構わないんだと思う。
実際、ポットで沸かしたての熱湯で煎れても、ちゃんと美味しい。もっと暑くなったら、水出しを試してみよう。
そんなことを考えながら、僕はテーブルに戻った。
印刷が終わっていたので、打ち出した紙束をクリップで留め、プリンターとノートパソコンの電源を落としてテーブルの隅にいったんどける。
「さ、休憩休憩……あちっ」
欲張ってたっぷりお茶を煎れたので、マグカップに口を付けると、縁まで驚くほど熱くなっていた。
当然、中のお茶もあつあつだ。
少し冷ましておくことにして、僕はテレビのリモコンに手を伸ばしかけ、途中でやめた。
東京の下町のアパートに暮らしていた頃は、すぐ前の道路をトラックが渋滞避けに使っていたので、走行音がうるさくて、仕事中はいつもテレビを点けっぱなしにしていた。
おかげで、政治家や芸能人のスキャンダルや家事のコツには無駄に詳しかったものだ。
でも、ここはとても静かだ。
たまに、幼稚園・保育園や小学校から帰ってきた子供たちの声が聞こえたり、廃品回収業者の車がややしつこいアナウンスをスピーカーから流しつつ通り過ぎたりするだけで、あとはしんと静まり返っている。
先輩の家が、表通りから少し入ったところに建っているからかもしれないが、とにかく耳障りな音というのがほとんど存在しない。
先輩の家に転がり込んできたばかりの頃は、昼間に目覚めるたび、あまりにも外の音が聞こえてこないせいで、世界中に僕だけしかいないような不安な気持ちになった。
今はすっかりこの環境に慣れてしまったので、東京住まいに戻ったら、むしろうるさくてイライラするかもしれない。
一年ちょっと暮らしただけで、僕は色んな意味で「芦屋ナイズ」されてしまったようだ。
なのに、せっかく有名な芦屋の桜の大部分も、噂に聞いた賑やからしい「さくらまつり」も、ミスってしまったのだけれど。
そんなことをまだうじうじと考えながら、僕はテーブルの端っこに置かれた黄色くて四角い缶を引き寄せた。
缶の蓋に書かれているのは、「鳩サブレー」という赤文字と、横を向いた白い鳩の絵。
言うまでもなく、「鎌倉 豊島屋」の銘菓だ。
ただし、今、中に入っているのは、絵と同じ形のさくさくしたきつね色のサブレーではなく、ゴチャゴチャと詰め込まれた色々なお菓子たちだ。
以前、二人がかりで四十枚近く入っていたサブレーを美味しく食べ終わったあと、遠峯先輩は、この缶を「白石のおやつ箱」と名付けた。
そして、自分用に買ってきたお菓子の中で気に入ったものや余ったものを、僕のために入れておいてくれるようになった。
先輩いわく、「作業の合間に甘いものを食うと、心も脳も効率よくリフレッシュできるぞ」だそうで、家にこもって仕事をする僕を思いやってくれたようだ。
先輩には、そういうマメで優しいところが昔からある。
正直、僕はここに来るまで、あまり甘い物に興味がなかった。
でも、甘党の先輩があれやこれやと買ってきては勧めてくれるので、今では、こうしてお茶を煎れ、缶を開けて中のお菓子を少しつまむのが、午後の習慣になっている。
缶の蓋を取った僕は、中身をひととおりあらためてみた。
仕事の行き帰りにコンビニで買ったらしき、ファクトリーメイドのクッキーやビスケット、それにおかきなんかも入っている。
「甘いもんとしょっぱいもんを交互に食うんは食の幸せやろ」というのが先輩のおやつ哲学なので、このおかきは、甘味の引き立て役といったところだろう。
ほとんどはこうした安価なお菓子で、たまに頂き物の高級菓子が交じる。
でも今日は……。
「うわ、なんか凄いのが入ってる」
僕は、缶の中でひときわ存在感を主張するアイテムを手に取った。
これは、明らかにコンビニで買えるものではない。おそらく、頂き物でもない。
僕が原稿の追い込みでうんうん唸っているのを見た先輩がわざわざ買ってきて、そっと入れておいてくれたに違いない。
それは、透明の袋に入ったバウムクーヘンだった。
小振りだけれど、いかにも人の手で焼かれたらしき個性を感じる。
袋越しに観察してみると、高さはせいぜい七、八センチ、直径もたぶん同じくらいだろう。よく見る円筒形のバウムクーヘンと違って、畳んだ提灯を二つ積み重ねたような形をしている。
両手で極端な瓢箪形を描いたときのように、バウムクーヘンの外側のラインにけっこう激しい凹凸があるのだ。
「どこの店のだろ」
外袋には楕円形の茶色いシールが貼ってあり、そこには“Stern”と書いてあった。たぶん、それが店名なんだろう。
「すたーん……?」
と首を捻りながら袋を引っ繰り返してみると、バウムクーヘンの底にあたるところにもう一枚、原材料を印刷した白いシールがあった。そこには、ありがたいことに今度はカタカナで店名が印刷されている。
「『シュターン』だった! かっこいい名前だけど、どういう意味だろ。ま、それはさておき」
興味をそそられはしたが、それは辞書を引く方向ではなく、どうやら強いこだわりがありそうなバウムクーヘンの味を確かめる方向にだ。
僕は席を立ち、背後のキッチンから果物用の小さなまな板とペティナイフ、それに鋏を持ってきた。
まずは鋏で外袋をチョキチョキと切り、バウムクーヘンを取り出す。乾燥を防ぐため、バウムクーヘンはさらにもう一枚のフィルムに包まれているので、それは手で注意深く剥がす。
次にバウムクーヘンの真ん中の穴に貼り付いた薄い銀紙をぺりぺりと引っぺがして、やっと切る準備ができた。
「さて、すたたたたんっと切っちゃいますか……って、ん?」
ふと気付くと、テーブルの上に、小さな紙切れが落ちている。どうやら、バウムクーヘンと一緒に入っていたものらしい。
「なんだろ。お、『バウムクーヘンのおいしいひみつ』ってか」
見れば、どうやらこのバウムクーヘン、本当にとんでもないこだわりの一品であるようだ。「焼く人」という項目には、職人の名前ばかりか経歴まで、ごま粒くらいの文字で印刷してある。
「ドイツで修業した、お菓子のマイスターなんだ。すっげえな。マイスターって、滅茶苦茶なるのが大変だって、ソーセージの職人さんに聞いたことがあるぞ。……あ」
ふむふむと興味深く職人のプロフィールを読み、何の気なしに紙片を引っ繰り返すと、裏面には、バウムクーヘンの美味しい切り方まで載っていた。
僕がやろうとしていたように縦にナイフを入れるのではなく、一センチくらいの厚みに、斜めにカットしろと書いてある。
物凄く面倒臭い。
疲れていることもあって、もう普通に切って食べてしまおうかと思ったけれど、危ういところで僕は踏みとどまった。
バウムクーヘンに手を着けたことに気付けば、先輩はきっと、ちゃんとおすすめどおりに切ったかどうか確認するはずだ。
だいたいのことには大雑把なくせに、スイーツに関しては、先輩はとにかく細かいしうるさい。僕がいいかげんな切り方をしたと知ったら、能面の生成みたいな顔で怒り出すに違いない。
そんなことで僕と先輩の関係が悪化して、「出て行け」なんて言われたら、凄く困る。
それに、こんなに凄い職人さんが丹念に焼いたバウムクーヘンだ、一度はきちんと切って食べてみないと失礼だろう。
「ええと、一センチの厚みってこのくらいの角度でいいのかな。おっ?」
ナイフを入れてすぐ、僕は意外な感触に驚いて声を上げてしまった。
塊で持ったときはしっかりした持ち心地で、しかも妙に軽かった。もしかして、パサパサして硬いのかなと思っていたのに、ナイフが吸い込まれるように入っていく。
まるでスプーンで掬うようにスムーズに切り分けた最初の一切れを、僕はしげしげと眺めた。
そういえば、よく見るバウムクーヘンのような外側の砂糖衣は、これにはかかっていない。
いちばん外側の焼き色は意外と浅い。内部のしましまの層はほどよく細く、生地はとてもきめ細かい。鼻を近づけると、強すぎないバニラの香りがふわっと鼻をくすぐる。
全部切ってから食べようと思っていたのに我慢出来ず、僕はそのままパクリと頬張ってみた。
「うわ」
また、驚きの声が出た。
全然、パサパサなんてしていない。しっとりしているけれど、油脂がもたらすものとは明らかに違う、もっと軽くて優しい食感だ。
紅茶にしておけばさらに美味しく食べられたかなとは思うけれど、そもそも口の中の水分が奪われているという危機感がない。
というか、驚くほどぱくぱく食べられてしまう。そして実際、食べたい気持ちを抑えられない。
あっと言う間に一切れを平らげた僕は、すぐさま再びペティナイフを手にした。
最初の一切れを切るのはややトリッキーだけれど、あとは薄く斜め方向にどんどん削いでいけばいいだけだ。
勢いのままに、僕はバウムクーヘンをすべて切り分けてしまった。
そして、マグカップの緑茶をお供に……そう、言い間違いでなく、お茶のほうをお供にして、夢中でバウムクーヘンを口に運んだ。
「……あ」
食べる前は、一切れか二切れで胸がいっぱいになりそうだなんて思っていたのに、皿に移すこともなく、まな板の上に置いたまま黙々と食べ続け、気付けば最後の一切れになっていた。
先輩に半分残しておくことすら忘れていた。しまった。
でも、缶の中身は好きに食べていいと言ったのは先輩だし、実際、物凄く美味しかったから食べてしまったのだし、これはきっと、先輩も喜んでくれるに違いない。
「うん、一切れだけ残すのも何だし、食べちゃえ」
僕は躊躇いなく最後の一切れを口に放り込み、ゆっくり解けるような不思議な食感とやわらかな甘みを味わいつつ、満足の溜め息をついた。
現金なもので、さっきまでの桜をめぐる鬱々とした気持ちは、ずいぶん軽くなっていた。
確かに甘いもののパワーは凄い。それが美味しければ、なおさらだ。
「先輩、ご馳走様でした」
今頃はまだ病院で眼科医の仕事に奮闘しているであろう先輩に両手を合わせて感謝し、僕は残りのお茶を飲み干すと立ち上がった。
そして、仕事道具を片付け、夕食の下ごしらえに取りかかったのだった。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細