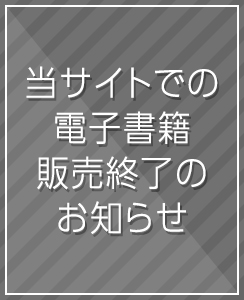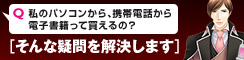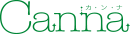狂犬ドルチェ
私のために蜜を出してください・・・
甘い甘い、甘い、・・・蜜を・・・
勤め先を辞め失意の中にいたパティシエの玲央は、
突然訪ねてきたラウロに、ホテルのパティスリーへ招かれた。
彼は支配人だという。
豪華な社宅に案内され、ラウロ自らが甲斐甲斐しく世話してくれる。
不審者達に襲われた時も、駆けつけた彼に救われた。
抱き締める腕に安堵しすがった玲央だったが、ラウロの青い瞳は獰猛な熱を孕んでいた。
貴方を貪り尽くしたいと、求められ……。
「貴方がお作りになる菓子よりも、貴方の方が遥かに甘い匂いがする」
かぷり、と立てられた白い歯が、玲央の靴下を引きずり下ろし、そのまま脱がせてしまった。露わになった裸の爪先の匂いを吸い込み、ラウロは端正な顔を恍惚に染め上げる。
「…ほら、甘い…」
「っ…、ラウロ、…さんっ…」
「甘くて…、甘くて甘くて甘くて……、我を忘れてしまいそうなほど……」
ぬるぅっ、と親指がラウロの口内に沈み込まされてゆく。爪と指の境目をなぞられ、喉を鳴らして吸い上げられた瞬間、股間がずくりと疼いた。
……や…、何で…、どうして、こんな時に……!
人間離れしたラウロの鼻は、きっと嗅ぎ付けてしまう。暴漢に襲われ、ついさっきまで震えていた玲央が、爪先をしゃぶられただけで勃起しかけていると。…先端から滲み始めた、先走りの微かな匂いで。
「駄目、…駄目、です…っ、ラウロさん…!」
はしたない有様に気付かれたくなくて、ラウロにだけは軽蔑されたくなくて、玲央は捕らわれた足を懸命にばたつかせた。だからラウロが名残惜しそうに親指を解放し、足を放してくれた時はほっとしたはずなのに、どういうわけか安堵と同じくらいの失望と不安が襲ってくる。
「……申し訳ありません。恐ろしい目に遭われたばかりの貴方に、こんな真似をするつもりは無かったのですが」
ラウロは嘆息し、起き上がりざま玲央に背を向けた。遠ざかっていこうとする男を、玲央は反射的に呼び止める。
「ラウロさん…、どこに行くんですか?」
「……警察に通報してきます。犯人はすでに都内から逃走しているでしょうが、アパートでの事件もありますから、併せて捜査はしてもらえるはずです」
立ち止まりはしたものの、前を向いたままのラウロに、玲央は激しい胸騒ぎを覚えた。ここで行かせてしまったら、二度と会えなくなってしまうような──。
「…行かないで、…ここに居て、下さい」
「事情聴取や実況見分には、私が応対します。その後は弁護士を代理人に立てますから、菊森さんが出て行く必要は…」
「そんなことじゃ、ないっ……!」
どこにそんな力があったのか。自分でも驚くような勢いで玲央は飛び起き、頑なな男の背に突進していた。あれほど軽蔑されたくないと願っていたのに、発情に火照りかけた身体を押し付け、分厚い胸板にしがみつく。
「き…っ、菊森、さん…」
「──玲央、って!」
もどかしさに悶えながら叫び、玲央は官能的な匂いのする背中に顔を埋める。
「玲央って…、さっきは名前で、呼んでくれたのに…!」
「菊森さん……」
「嫌だ…っ、嫌だ……!」
名前で呼んでくれなくちゃ嫌だ。玲央を置いてどこかへ行っちゃ嫌だ。ずっとここに居てくれなくちゃ嫌だ。
次から次へと、子どもじみた駄々ばかりぶちまける自分に、心底嫌気がさした。二十歳もとっくに過ぎた男が、一体何をしているのか。しかも相手は家族でも、友人ですらない…ただのビジネスの相手なのに。
「……酷い方だ、貴方は」
ややあって、ぽつりと落とされた呟きに、玲央は打ちのめされた。呆れられ、軽蔑されて当然だ。わかっていても引き攣れたように痛む胸が、次の瞬間、どきりと高鳴った。
「ご自分がどれほど私に忍耐を強いているのか、おわかりにならないなんて」
「え、…っ……」
「私の理性がもう少し薄弱だったら、貴方は今頃、私の精を腹に溜め込まされたまま、朝な夕なベッドで泣かされ続ける羽目になっていましたよ」
ばっ、と玲央がラウロから身を離したのは、本能ゆえだろう。ラウロの言葉は決して冗談ではない──本気なのだと、敏感に察したのだ。肉食獣に狙いを定められた、哀れな獲物の特有の鋭さで。
そしてラウロは、逃げ出そうとする獲物を捕らえるのに、たった一言発するだけでいい。
「──玲央」
「ひ、……っ!」
こちらからねだったはずの呼び声が、玲央をその場に縛り付ける。ほんの二音の己の名前が、こんなに蠱惑的な響きを帯びるなんて知らなかった。
「…選んで下さい。このまま私を行かせるか、それとも……傍に置くか」
「…えら、ぶ…?」
「もし私を行かせるなら、何も無かったことになります。今までと何も変わらない。…けれど、あくまで私をお傍に置くとおっしゃるのなら……」
背中を向けたラウロが、ぐっと拳を握り締める。
「──もう、我慢はしない。貴方が作る菓子のように、貴方も貪り尽くします。今日だけではなく、明日も明後日も…死ぬまで、貴方を求め続ける」
「…、ラウロさん…」
「……その覚悟が無ければ、私のような男を気安く傍に置こうなどと思わないことです」
ラウロの紡ぐ言葉の一つ一つが、不可視の炎となって玲央の肌を内側からじりじりと炙ってゆく。
……求められていたのは、菓子だけじゃなかったんだ。
玲央が菓子を貪るラウロに官能を煽られたように、ラウロもまた、玲央を欲望の対象として見詰めてくれていた。そう思うだけで見知らぬ男たちに襲われた恐怖は消え失せ、代わりに未知の感覚が玲央を満たしていく。宣言通り、死ぬまで玲央を喰らい続けるだろう男が恐ろしくてたまらないのに、その熱を一番近くで感じたいなんて──。
「……傍に、居て」
自ら獣の牙にかかるために、玲央はラウロのジャケットの裾を引いた。広い肩が小さく震えた次の瞬間、馴染んだリビングの空気が一変する。今までかろうじて抑え込んでいた情欲を、ラウロがその身に燃え上がらせたせいで。
「…ただ寄り添うだけでは、済みませんよ?」
「わかってる。……俺も、ラウロさんが欲しい、か、…ら…っ!?」
言い終えるが早いか、振り返ったラウロが玲央を勢い良く抱き上げ、ずかずかとリビングを横切った。普段からは考えられない乱暴さで玲央の部屋のドアを蹴破り、玲央ごとベッドに乗り上げる。
爛々と光る青い目が、玲央を真上から射竦めた。
「…玲央、玲央、玲央、…私の、愛しい玲央…」
「い、…やぁ…っ!」
ベルトの金具を外し、引き抜いたところで、ラウロの理性は限界を迎えたようだった。ボタンをズボンのウエストからむしり取り、ファスナーごと前を引き裂いて、露わになった下着をずり下ろす。
「あああ……、はぁっ…、あ、玲央、…玲央…っ…」
男にしてはぽってりとした唇から、ぼたぼたと涎が滴り落ち、玲央の剥き出しの性器を濡らした。瞬く間に濡れそぼった肉茎に、ラウロは脇目もふらずしゃぶりつく。
「…あぁ、…っ、ラウロ、さん…、駄目ぇっ…」
兆していたものを熱い口内に包み込まれ、それだけで絶頂に押し上げられそうになりながらも、玲央は股間でうごめく頭に指を埋めた。最初はなかなか肉茎に喰い付いて離れようとしなかったラウロも、何度も黒髪を引っ張るうちに、不承不承顔を上げる。
「……貪り尽くしてもいいと、おっしゃいましたよね?」
- プラチナ文庫
- 書籍詳細