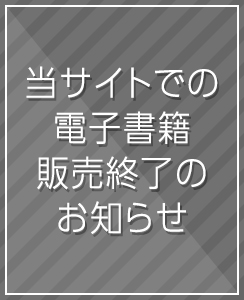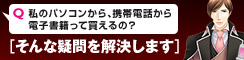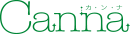闇を呼ぶ声 -周と西門-
溺れそうなときは、つかまれ。
憑いた霊を引きはがす呼児の周には、それを彼岸へ封じる戻児で唯一の対でもある双子の妹がいた。その妹を亡くして以来、周は力を使おうとせず鬱々と生きている。突然同居することになった親戚の西門にも、胡散くささしか感じなかった。けれど、胸中の痛みを覗かせる彼の言葉は、周の心をほぐしていく。戻児である西門と仮の対となり、妹の死に繋がる怪異を追ううちに周は……。
「おまえら呼児は、それがなにかわからん状態で怪異を呼び出すやろ。なにが現れるかわからん、それってえげつない怖さやんか。おまえら、ようそんなことするわな」
「……呼児はそういうものだ」
「うん、そやろ。呼児はたいがいそう言いよんねん。そやからこっちも覚悟決めるんや」
「覚悟?」
「おまえら呼児が命懸けで呼び出すんやから、こっちも命懸けで封じたるて思う。呼児と戻児は、そういう言葉にせん約束事の上で対になるんや。犠牲になるとか、ならんとか、そんな次元の話やないねん。少なくとも俺はそう思っとる」
わずかに間をはさんで、
「そう思うようになった」
と西門は言い直した。
「……前はそう思ってなかった?」
「せやなあ。てか、そんなこと考えもせんかった」
「……なんで今はそう思うの?」
「考えなあかんようなことがあったんや」
なにがあったのか、問うことがはばかられるような苦みを声音から感じた。
自分と西門はひと回り年齢が離れている。自分がまだ体験したことのない、西門の十二年という時間。それは言葉という形では伝わらないのだろう。
自分も本当はわかっている。
薫が自分を恨むなんてありえない。
けれど、そうなのかと受け入れて楽になることはできない。
誰に慰められても、言葉を尽くされても、自分で自分を許せない限り、この罪悪感と自己嫌悪は消えない。そういう気持ちをうまく言葉にできない。言葉にしても、そんなのただの自虐だと言われるだけで──。
「けど、そう思うか思わんかは周の自由や」
「……え?」
「俺がどんなけまちがいない言うても、おまえがそうは思えんかったら一生呑み込めんままなんや。けどそれもまたおまえの生き方や。誰もそれを否定する権利なんかない」
「……無駄だってわかってるなら、なんでそんなこと言うんだ」
「言うか言わんかは俺の自由。聞くか聞かんかはおまえの自由」
「なんだそれ。なんの意味があるんだよ」
「いろんな意見があっておもろいなあってことや」
「…………なんだよ、それ」
後ろからすっぽりと包まれる形でつぶやいた。
自分の心はとてもせまい。だからそれが素晴らしい言葉であるほど、容量不足で入ってこない。西門の言葉は無責任で、片手で持てるくらいの軽さなので、自分のせまくて融通のきかない心の中にも入ってきてくれる。
「前も似たようなこと言うたけど、まあ覚えてへんやろ」
そう言われて、ふと思い出すことがあった。
──無理して出んでええやん。
──それもまた人生やん。
西門に連れられていった近所の小料理屋で酔っぱらい、出口が見つからない、出口があっても出ていいのかわからないと言う自分に、西門はそう言ったのだ。
「おまえベロベロやったしなあ」
「酒がまずかったことは覚えてる」
自分の醜態まで思い出して恥ずかしくなった。
「まずい言うわりにグイグイいっとったな。揚句に俺にキスまでしよって」
「まだそんな寝言を言ってるのか」
「ほんまやん。ファーストキスやて言うとったで」
「俺のファーストキスが本当にあんたなら、絶望で死ぬしかない」
「おお、そうか、ほな絶望せえ。けど死んだらあかんで」
死んだらあかんー、死んだらあかんーと喉飴のCMみたいな節の歌を聞きながら、じわじわと口元がゆるんでいく。真面目な話をしていたはずなのに、西門と話しているといつの間にかこんなふうになる。西門と出会ってから、自分はよくしゃべるようになった。
「……生きてるだけなのに、しんどいな」
力が抜けてしまい、無防備な言葉がこぼれ落ちた。
「みんなそうやて。楽に生きとるやつなんておらんやろ」
「……そっか」
みんな幸せなのに、自分だけが苦しいと思うと余計苦しくなる。でもみんな苦しいなら、自分も苦しいままでもいいかもしれない。ネガティブな思考に思わず笑った。
「なに笑っとんのや」
「俺は暗いなと思って」
「今さら気づいたんか?」
「昔から知ってる」
周は身体を反転させて西門と視線を合わせた。
「あんたもそうなのか?」
「うん?」
「呑み込めずに苦しいことが、あんたにもある?」
西門の表情がわずかに変化した。豆電球の薄茶色い闇の中で、いつも柔和な口元に苦みが広がっていくのを見ながら、聞いたことを後悔した。
「……ごめん。言わなくていい」
そう言いながらも、西門のことをもっと知りたいと思った。
他人にそんなことを思ったのは初めてで、戸惑った。
この気持ちはなんだろう。
薄闇の中、至近距離からじっと西門の顔を見つめた。
自分たちの年齢差を考えると、西門の中に在るものや、考えを理解できる日はこない。永遠に追いつけない。そう思うと、もやもやした重ったるいものが胸ににじんでいく。
「……どうしよう」
「うん?」
「……なんか、胸が気持ち悪い」
「へ? 吐きそうなんか」
「ちがう。けどなんか気持ち悪い」
西門の顔を見ていると、なんだかそわそわして落ち着かない。
「吐くんやったら、トイレ連れてったろか?」
「いい」
「水持ってきたろか?」
「いい」
気持ち悪いけれど、そういう気持ち悪さとはちがう。
「なんか調子悪いみたい。もう寝る」
背中を向けると、また後ろからぬいぐるみみたいに抱きしめられた。いつもの体勢だし、もう顔も見えてない。なのにさっきより余計に胸が気持ち悪くなった。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細