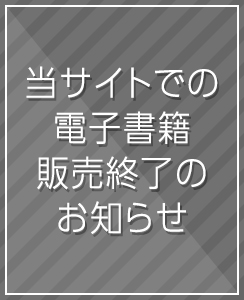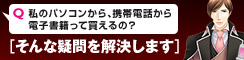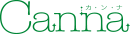純喫茶あくま 天使と恋とオムライス
この飯テロはあくま級!
漆黒の翼を持つ自称・悪魔な吾聞が切り盛りする「純喫茶あくま」。かつて聖職者を志していた澄哉は、そこで吾聞と契約し住み込み店員となった。おそらく恋人関係でもある。そんなある日のこと、吾聞の双子だと言う客が訪れた。純白の翼を持つ彼はプリンアラモードを頬張り、“恋のやり方”を聞く。問い詰められた澄哉は恋心を告白するが、無反応な吾聞の気持ちはわからなくて……。
喫茶店とはいえ、「純喫茶あくま」は夕方から明け方にかけて営業するため、食事目的でやってくる客も多い。
普通の喫茶店よりメニューの数が豊富な分、作り置きできるものはまとめて仕込み、小分けにして冷凍しておくのである。
カレーは人気のメニューであり、しかも大量に作って寝かせておいたほうが、味がよくなる。だから、週に二度ほど、大きな寸胴鍋一つ分を仕込むのだ。
オムライスを大急ぎでやっつけた澄哉は、重い寸胴鍋をコンロに乗せて火にかけ、後から大きな計量カップで水を何杯か注ぎ入れた。
その横では、吾聞が鶏の手羽中を大きなフライパンで焼き付けている。隙間に置かれ、香ばしい香りに色を添えているのは、ひとかけのニンニクだ。
皮にいい焼き色がつくと、吾聞は鍋に手羽中をどんどん放り込み、また次を焼いていく。
「いい匂い」
そう言いながら、澄哉はシンクでタマネギと人参の皮を剥き、セロリを洗った。
この店のカレーには、チキンを使う。
大量の手羽中を香味野菜と共に茹でてから濾し、油を取り除いて、滋味深いスープをとる。
それをベースにして、数種類の市販品を混ぜ合わせてカレールーを作り、そこに、茹でた手羽中から肉だけを外して加える。
さらに、火を通したタマネギと人参、それに大きめに切って揚げたジャガイモを足して、客に提供するのである。
骨付きの鶏肉から驚くほど豊かな味わいの出汁がとれるので、客の評判も上々で、澄哉も、まかないで食べるのを密かに楽しみにしている。
「吾聞さん、香味野菜、ここに置きますね」
刻んだ香味野菜を入れたアルミのバットをコンロの横に置くと、澄哉はいったん店の外に出た。
扉の脇に、大きな段ボール箱と、発泡スチロール製の保冷箱が置かれている。
近所のスーパーマーケットが配達してくれる食材だ。足りない食材は買いに出るが、ほとんどのものは、この配達でまかなえる。
「よいしょ……っと」
澄哉は両手で箱を一つずつ持ち上げ、カウンターの中の厨房に運んだ。箱を開けて、納品書と実際の品物を一つずつ照らし合わせ、確認する。
今ではすっかり、お手の物になった仕事の一つだ。
「あれ、吾聞さん。今日、合挽肉もいっぱい来てますよ。煮込みハンバーグの仕込みも、やっちゃいますか?」
吾聞は黙々と手羽中を焼きながら、背後の澄哉に振り向かず答える。
「どうせ、手羽中を煮るのに時間がかかる。その間にやってしまえばいい」
「わかりました。じゃあ、いったん挽肉は冷蔵庫に入れて、タマネギを刻んでおきますね。……あ、そうだ」
「何だ?」
やはり鍋のほうを向いたまま問いかけてきた吾聞に、澄哉は床にしゃがみ込んだままで言った。
「これまで煮込みハンバーグを出すたび、何かが足りないような気がずっとしてたんですよ」
「足りない?」
「はい。さっき、オムライスを見たときも、何かが足りないって同じように感じました。で、今、わかったんです。緑色が足りません。ほら、美味しそうな色の取り合わせは、黄色と赤と緑って言うでしょう?」
吾聞は菜箸を右手に持ったまま、軽く背後を振り返る。
「そうなのか? 俺は初耳だが、なるほど、オムライスは黄色と赤は既にある。煮込みハンバーグは……」
「ハンバーグは赤、付け合わせの人参グラッセが、一応黄色、かな」
「なら、煮込みハンバーグには、茹でたブロッコリーでも添えればいいだろう。確かに、オムライスにも緑がないな」
澄哉はちょっと得意げな笑みを浮かべ、立ち上がった。
「そうでしょう? オムライスをメニューに復活させるなら、ブロッコリーもいいけど、やっぱりグリーンピースかな。上に、三、四粒乗ってるだけで、ずいぶん雰囲気が……」
「駄目だ」
澄哉としては、いい提案をしたつもりだったのだが、吾聞はにべもなく撥ねつけ、再びフライパンに向き直ってしまう。
その取り付く島もない言い方をむしろ不思議に思って、澄哉は吾聞の傍らに立ち、整った横顔を見上げた。
「どうしてです?」
それに対する吾聞の返答は、驚くほどクリアだった。
「嫌いだからだ」
「えっ?」
「俺は、あの緑色の豆が嫌いなんだ」
吾聞は、苦虫を噛み潰したような顔つきで、同じ言葉を繰り返す。澄哉は、ビックリして、優しい目をパチパチさせた。
「グリーンピースが? 甘くて美味しいじゃないですか」
「あの、妙に甘いところが嫌なんだ」
「へえ……。吾聞さんにも、嫌いな食べ物があるんですね」
やけに感心した様子の澄哉を横目でジロリと睨み、吾聞は吐き捨てた。
「当たり前だ。好き嫌いはそれなりにあるぞ」
「そうなんだ。っていうか、好き嫌いは自慢できることじゃ」
「だからこそ、人間はお前を選んで喰っている」
「!」
自分を窘めようとしていた澄哉の顔がみるみる赤らんでいくのを見て、吾聞はしてやったりの笑みを浮かべた。
「何だ、不満か? 手当たり次第、誰でも好き嫌いなく喰らえとでも?」
「……ッ」
澄哉は赤い顔のまま、酷く困った表情を浮かべた。何度も口を開き掛けては閉じ、そしてどうにか、悔しそうに言葉を絞り出す。
「ずるいですよ、そういうの」
「何がだ」
「そんなことを持ち出されたら、好き嫌いは駄目ですなんて言えないじゃないですか」
「そうか?」
意地の悪い声でそう言うと、吾聞は菜箸を置いた。その手で澄哉の細い腰を捕らえると、何か言いかけた唇を、自分の冷たい唇でピッタリと塞ぐ。
「ん……っ」
だが、目を白黒させる澄哉が暴れ出さないうちに、吾聞はあっさりと唇を離した。それでも澄哉の腰に回した手は離さず、熱くなった耳介を軽く食んで低い囁きを落とす。
「なら、人間はお前を選り好みしておいてやる。その代わり、忌々しい豆についてもとやかく言うな」
「……ホントに、ずるい」
恨めしげに呟き、そのくせどこか幸せそうな面持ちで、澄哉は吾聞のシャツの二の腕に額を押し当てた。
自分でも、不平を言っているのか甘えているのかわからなくなってくるが、わからなくてもいいような気がするのが不思議だ。
そんな風に、穏やかに静かに日々は続いていくのだと、澄哉は思っていた。
それがいかに甘い考えであったかを彼が思い知るのは、わずか数日後のことである。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細