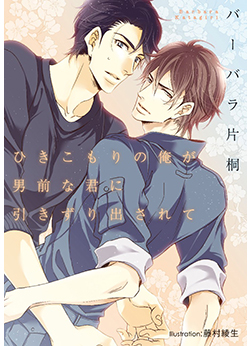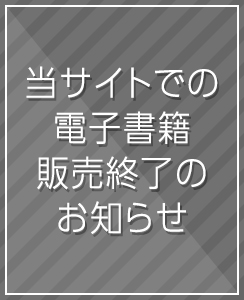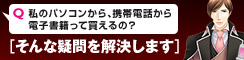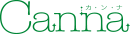ひきこもりの俺が男前な君に引きずり出されて
書籍紹介
ね、先っぽだけ……入れていい?
ひきこもる元検事の英輔は、ドアを蹴破り乱入してきた男に布団から引きずり出された。ひきこもり更正の仕事をしているという、その鋭い目つきの男は、初恋相手である悠真だった。
外は怖いが、繋いでくれた彼の手は温かく安心した。悠真が一緒にいてくれるなら──。そう思い始めた時、ひきこもる原因となった事件へのリベンジを誘われた。怯えて拒否するも、悠真は引き下がらず…。
立ち読み
「ふが……!」
鼻を押しつぶされて英輔はうめく。さすがに、顔面を足蹴にされるとは思っていなかった。
悠真は足にさらに体重をかけ、脅迫するように声を潜めた。
「起きるんだな?」
「起き……ます! 起きます……!」
こんなふうにされたら、もう従うしかない。
顔から足をどかされ、ジャージを投げつけられたから、英輔は不承不承身体を起こしてそれに着替えるしかなかった。
顔を洗って歯を磨くのを監視され、急かされたのちに、英輔は離れから連れ出される。
一度コンビニに行ったことで、外への抵抗はだいぶ薄れていたが、敷地内から公道に踏み出すときにまた躊躇した。
あのときは、夜だった。だけど、今は朝だ。すでに明るいから、英輔のこの姿が誰からも丸見えになる。
それでも、悠真が躊躇なく歩き始めるので、英輔は従うしかない。だが、つないでくれない手がやけに心細い。軽く握りこんで、ぶらぶら振る。
「どこ行くの?」
「河川敷」
「え?」
「散歩って言っただろ」
家からさして遠くないところに、河川敷があった。そこにはランニングコースや広いグラウンドやゴルフコースがある。
──河川敷、か。
そこならばあまり人がいないから、問題ないかもしれない。
だが、朝の住宅街を突っ切るのが問題だった。夜なら闇が全てを覆い隠してくれるが、今の時刻は通勤通学やゴミ出しのために近所の人とバッタリ顔を合わせる可能性があった。
しかも、英輔はジャージだ。
仕事もせずにこんな姿でぶらついているのを見られたら、自分がまっとうな勤め人ではないと相手にすぐにわかるだろう。そうしたら、英輔にまつわる過去の報道を人々は思い出すかもしれない。そう思った途端、気持ちが萎えた。
外へは出たくない。出られない。
「……俺、いいよ」
英輔は足を止め、軽くうなだれた。
だが、途端にジャージの胸元をわしづかみにされて、前へと引っ張られた。
「ふざけたこと言ってんじゃねえよ」
その勢いに負けて、英輔は二、三歩前に出る。それだけで、ざわっと全身に冷たい戦慄が広がった。これ以上は歩けそうもないように感じられて、英輔は生唾を呑みこむ。だが、自分はこの場を克服できる方法を知っている。
英輔は震える手を悠真に差し出した。
手を引いてくれなければ動かない、の意思表示だ。コンビニに行ったときには、悠真が手を引いてくれた。そのときの安堵感が残っている。あれがなければ、自分は動けない。
だが、悠真はその手を冷ややかに見やるばかりだった。
「てめえ。……今は朝だぞ」
「……そうだな」
「爽やかな朝に、男が二人、手ェつないで外を歩くつもりか」
その言葉に、英輔はハッとした。
確かにそれは問題だ。何やら、誤解されそうな気もする。だが、そんなことよりも、自分がこのままでは外を歩けないことのほうが大問題ではないだろうか。
「だったら、外行かない」
行くか行かないか、悠真の選択次第だ。
道の端にはこんな早い時刻からところどころにゴミが置かれて、カラス除けの黄色いネットがかけられていた。こんな状態では、いつどこから近所の住人が出てくるのかわからない。
すると、小さなため息とともに手が握られた。
「行くぞ」
ぐい、と手を引っ張られて、英輔も前に踏み出す。
こんなでかい図体をしているのに、自分よりも背の低い悠真に手を引かれて歩いているなんて、少し恥ずかしい。だけど、握られた手から広がるぬくもりの嬉しさのほうが、恥ずかしさを上回っていた。
──大丈夫、誰にも会わない。
英輔は自分にそう言い聞かせようとする。
離れを出る前に時刻を確認したら、まだ六時半だった。その時間から外をうろつく人々は多くないはずだ。
だが、朝の散歩を習慣にしている人は一定数いるようで、近くの路地から犬を連れた年配の男性が出てきた。
英輔はすぐに目を伏せて犬の姿だけを見た。男が誰なのか確かめることもできないまま、手を引かれてとぼとぼと歩いていく。
──どうしよう。『おや、君は』と声をかけられたら。
何より知っている人が怖い。
英輔の過去を知っている人間を避けたい。
悠真の手を握りしめた手から力が抜けないほど、全身が緊張していた。それでも、足を止めずにいられるだけ、自分は成長しているかもしれない。
すれ違う一瞬、英輔はどうにか声を押し出した。
「おはよう……ございます」
声はかすれていて、ちゃんと相手に聞こえたのかもわからない。すぐに返事があった。
「おはよう」
相手が知っている人なのか、そうではないのかもわからなかった。犬には見覚えがない。
だが、ちゃんと挨拶を交わせただけで、驚くほど心が楽になった。
一つミッションをクリアした気分で高揚したまま、誰でもドンとこい、という気分になれた。なのに他にすれ違う人はいないまま、河川敷まで到着する。
見晴らしのいい土手の上に立った英輔は、ようやく悠真の手を離して深呼吸した。すっかり日は昇っていて、澄んだ朝の空が広がっている。
河川敷に来るのは、本当に久しぶりだ。
朝の空気はとてもすがすがしく、流れる河の水は記憶にあったものよりもずっと綺麗になっているように思えた。
だが、休憩する間もなく、悠真に宣言される。
「じゃ、筋トレするぞ……!」
──筋トレ……?
何を言われているのかわからない。
だが、悠真が指さしたグラウンドの一角には、筋トレ用の遊具が設置されていた。
そこに案内され、その遊具の使い方を教わりながら、悠真は否応なしに筋トレをさせられることになった。
ずっと身体を動かすことなくひきこもっていたから、腕立て伏せもまともにできないぐらいだ。このような遊具がなかったら、さらに困難だったことだろう。
限界まで追いこまれたところで、「これくらいでいいだろう」と悠真の声が響く。
みっちりと汗をかいた英輔にタオルと水を差し出しながら、悠真は顎をしゃくった。
「少し離れたところに、いい感じの桜並木がある。そこまで散歩するぜ」
まずは休憩したかったが、嫌だと言っても悠真に逆らい切れないことはわかっていた。
それに桜と言われて、英輔の心は少し動いた。この四年間、花見どころではなかった。
悠真と一緒だったら、余計に桜は綺麗に映るだろう。
「ああ。……行く」
河川敷はマラソンコース以外にあまり人はいなかった。
もしかしたら家からより遠く離れたほうが、自分を知っている人と会う可能性は減るかもしれない。
英輔の家は代々名士を輩出し、何かと近所に知られた存在だった。英輔はそこの長男であり、幼いころから父に連れられてさまざまな行事に出席してきた。
四年も経てば人々の記憶から消えると悠真は言っていたが、それでも不安が消えない。
──だけど、不起訴だったんだし……! 俺は後ろ暗いことは、何一つしていない。
悠真がいれば、少しずつやり直せそうな気がしてくる。
ゆっくりと英輔は、悠真の後について歩を進める。踏みしめる芝生は柔らかく、吹く風は爽やかだ。
「ほら。あそこ」
悠真が指し示した桜は、かなり離れた土手の上にあった。遠くからでも、そのあたりが薄ピンク色にかすんでいるのがわかる。歩いてもなかなか近づいてこなかったが、二十分ほどひたすら歩いてその木の下に立った。
「すごいな」
枝もたわわに、桜が咲き乱れている。ちょうど満開だった。
英輔は顎を上げて、咲き乱れている花を凝視する。花の勢いに圧倒される思いだった。
朝の空気は澄んでいて空はあくまでも青く、いつまでも桜を見ていたくなる。
「散るまで、毎日ここまで散歩しようか」
悠真に言われて、英輔はうなずいた。
花の下で悠真はリラックスしているのか、柔らかく笑っていた。その表情に見とれそうになって、慌てて花に視線を戻す。
大きく深呼吸した。
──大丈夫だ。
少しずつ、自分は変わっていける。悠真がいてくれれば。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細