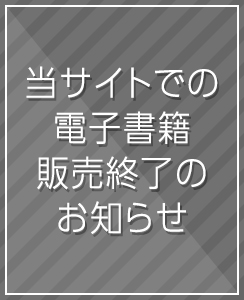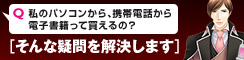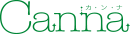或る猫と博士の話。
書籍紹介
ご主人さまは、とってもいい匂いがします。
ある施設で生み出された、人と猫の遺伝子を持つリュリュ。葬るべき対象だったが、殲滅計画を率いたユーリは、密かに彼を連れ出した。健気な仔猫のリュリュが可愛くてならなかった。成長しユーリより逞しくなっても変わらず可愛く、愛しく思っていた。けれど──「ねえ、ご主人さま。俺、もう子供じゃないんだよ?」いつしか、ユーリに注がれる視線に熱が孕むようになって……。
立ち読み
「リュリュがいてくれなければ、私の人生はもっとつまらないものになっていただろうね。リュリュにはとても感謝しているんだ」
「ご主人さま……!」
リュリュがふるりと身震いする。
ようやく手の届く距離まで近づいてきたので鼻先をつついてやると、ユーリの肩口にそっと頭が擦り寄せられた。
仔猫のような仕草に愛おしさが募る。
だから。
ユーリは青空を分断する鉄骨を見上げた。
「だからこそ、君には幸せになって欲しい」
「ご主人さま」
「その呼び方は止めなさい。私は合成獣計画の連中とは違う。主として君を使役する気はない」
「じゃ……じゃあ、ユーリ、さま……?」
ざわり、と。
リュリュの柔らかな声がユーリの名を紡いだ瞬間、膚が粟立った。
実験体であった頃の刷り込みを切り離して欲しい。ただそれだけを望んでの言葉だったのに、ユーリさまと呼ばれた瞬間、なにかが変わってしまったような気がした。
「? 俺、なにか間違った? どうして赤くなるんですか?」
「いや……」
失敗した。
ユーリは秘かに狼狽する。
呼び方というものは、関係性の象徴だ。
一語違っただけで、まるでずっとかけていた色眼鏡を外したかのように世界が違って見えた。リュリュがこれまでとは違う、別の存在のように目に映る。そんなことがあるわけないのに。
ユーリは小さく咳払いして、気を取りなおした。何事もなかったかのように続ける。
「なんだか照れくさかっただけだよ。君はどうしてもご主人さまと呼ぶのをやめてくれなかったから」
「だって俺はご主人さまに支配されたかったんだもの」
肩口にぐりぐりと頭が擦りつけられる。
「これからは自分自身のために生きることを考えなさい。私もそのために努力する」
「でも」
「時々思うんだ。もし私が死んだら、リュリュはどうなるんだろうって」
リュリュの背筋が伸びた。
「そんなこと言うのはやめて欲しいんですけど……!」
「だが、君は私よりずっと若い。きっと私の方が先に死ぬことになる。そうしたら君はひとりぼっちだ」
太陽の光が燦々と降り注ぐ屋根の上、リュリュは愕然とした顔をしている。現在が永遠に続くと思っていたのだろう。少し前のユーリと同じように。
「ニンゲンではないとはいえ、君はあらゆることに優れている。私のようなくたびれた男に尽くすだけではもったいないよ。もっと広い世界を得て、人生を共に歩める相手を探した方がいい。そうできるようにいつかするから、一緒に頑張ろう」
リュリュは納得したようには見えなかった。なにか反論したいけれど、なにを言ったらいいのかわからない──そんな顔をしている。
「さて、下に下りようか。ヴァーノンに大分食い荒らされてしまったが、エクレールを食べよう」
「俺は!」
唐突に言葉を発したリュリュがユーリの腕を掴んだ。
「うん?」
「俺はなにができるようになっても、ご主人さまの傍を離れる気はないです」
「リュリュ」
「だって、好きなんだもの」
「リュリュ、私は男なんだぞ? おまけに君よりうんと年寄りだ」
「そんなの関係ありません」
「リュリュ」
少し声を大きくすると、リュリュは色の薄い唇を子供のように尖らせた。
「でも、ご主人さま。もし、普通の子に生まれついたとしても──最初から周りに女の子がいっぱいいたとしても、俺は絶対ご主人さまに恋してたと思うんです」
「どうかな」
気のない返事にリュリュは眉を上げる。
「だってご主人さま、優しいし。初めて会った時、俺、汚くて酷い匂いさせてたのに、ご主人さま、厭な顔ひとつしなかった」
「いたいけな仔猫が吐瀉物にまみれて泣いていたら、誰だって優しくするさ」
「それに、俺をだっこしてくれた。シセツでもね、ご主人さまたちがだっこしてくれることはあったんだけど、綺麗な白い子だけだったんです。俺はこんな変な毛色だから一度もしてもらえなくて。ご主人さまが抱き上げてくれたの、嬉しかったなあ……」
切なげに微笑むリュリュに胸が詰まった。
抱きしめたいという衝動を殺し、ユーリは目を逸らす。
「ヴァーノンだって君をだっこしてくれただろう?」
はぐらかし続けたせいだろう、リュリュの目が苛立たしげに細められた。
「それからご主人さま、時々髪を掻き上げるでしょう? ちらりと見えるここのライン、俺、すごく色っぽくて好き」
長い灰色の髪の下に忍び込んだ指にうなじを撫でられ、ユーリは身を竦めた。
「こら。さっきご主人さまと呼ぶなと言ったばかりだろう?」
ユーリさまと呼ばれずに済んでほっとしたことなどおくびにも出さず、ユーリはリュリュを窘める。だが、リュリュはきれいに無視した。
「それから目尻に皺を寄せて笑む顔も、寝起きが悪くて、起き上がってからもしばらくぼーっとしているところなんかもすごく可愛い」
気がつくと、腰にリュリュの両腕が回されていた。
「──ねえ、ご主人さま。俺、もう子供じゃないんだよ?」
じいっとユーリを見つめるリュリュは真剣な顔をしている。
同じように座っているのに目線の高さが違う、大きな躯。逃すまいとユーリを捕らえている手ですら出会った頃とはまるで違っていて、力強い。
リュリュが幼かった頃には感じたことのなかった緊張を覚えたが無視し、ユーリは淡く微笑んだ。
「毎日顔を合わせているんだ。知っているよ」
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細