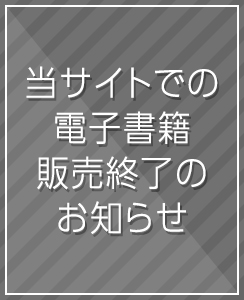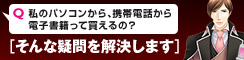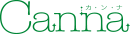それは初恋すぎるでしょう。
書籍紹介
手を握られて、顔が熱くなった。これがオッサンの反応かよ!?
デザイナーの迪と銀行に勤める阿川は、二十年来の付き合いだ。高校生の時には、ドキドキしながら手をつないで歩いた。ずっと側にいて親友以上に大切、けれど恋人未満。そんな存在なのだ。大人になった今、胸に燻る想いを計るように、阿川は意味深なことを言う。迪もまた試すように彼を見つめる。十代の頃のように、恋の情熱で突っ走るなんて、怖くてできずにいたが……。
立ち読み
「俺にはミチの作品を、一刻でも早く手にする権利がある。そうだろう?」
「意味がわからん。なんだ、その権利って。どこから出てきたんだ」
「あるだろう、俺にはその権利が。んん? あるだろ?」
「おまえが、俺に?」
「二十年、おまえのそばにいる俺だから、の権利だ」
「…ああ……、ある、かも……」
迪はあやふやにうなずいた。二十年、阿川は迪の、迪は阿川のそばにいる。物理的な距離ではなく、心の距離として、この二十年、一度も遠く離れたことはない。それは親友という簡単な言葉ではくくれない、なにかもっと濃密な感情を互いに持っているからだが、そういう関係を端的に言い表わす言葉が見つからない。あえていうなら、恋情、になるのかもしれない。けれどそれをわざわざ相手に確認できる歳では、自分たちはもうない。
(だいたい確認てなんだよ。千鶴にも元カノにも、付き合う前に、好きなんだけど、なんて告白したこともないよ)
女性とは、なんとなくお互いに好意を持って、デートを重ねて、これは付き合ってるよなと確信できた時に、ちゃんと付き合ってほしいと、相手を安心させるために言葉にして気持ちを伝えてきた。阿川を相手に、それをどうやればいいというのか。
(二十年だぞ、二十年。歳なんか、もう三十五だ、オッサンだ。中年だぞ。お互い彼女がいて、結婚だって考えてるんだ)
でも、迪にとって阿川は、死ぬまでそばにいてくれなければ困る存在だし、阿川も同じように思ってくれていることはわかる。しかし、だからこそ、二十年も互いの一番身近にいるというこの関係を、どう言い表せばいいのかわからないのだ。
(十七のあの時なら。自分のことさえ考えていればよかった、あの時なら。俺はたぶん、おまえに言ってたよ、阿川。好きだってさ)
だがそのタイミングを逸してしまったのだ。たぶん、もう永遠に。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細