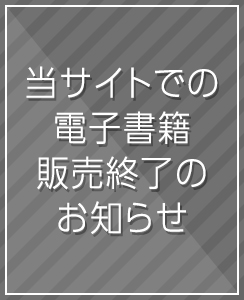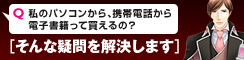累る-kasaneru-
書籍紹介
気持ちも身体も、もう離れられないと訴えている。
異母弟の奏人を母の虐待から庇い、夢に魘されると共に眠り宥めてきた七緒。ふたりが大学生となった頃、奏人から恋情を告げられ戸惑うが、七緒もまた彼が愛おしかった。けれど、夢を見た。奏人の夢と共通点があるようだが、徐々におぞましく苦痛に満ちていく夢。奏人に抱かれている時だけは、それから逃れられた。なのに夢が進むにつれ、恐ろしい疑念がこみ上げてきて……。
立ち読み
「……ま、毎晩、おかしな夢を見る」
口にしてしまえば、もう留めようがなかった。
「最初は山の中の建物にいるだけで、でも、だんだんおかしくなってきて」
鍵のかかった扉、格子のはまった窓。外に出るときは足首を紐につながれ、夜になるとやってくる見知らぬ男たちに好き放題される。毎晩、毎晩、それが続く。
「もう眠りたくない。寝たらまた夢を見る」
声を引きつらせながらしがみつくと、抱きしめる奏人の腕にも力がこもった。どんどん強くなって、息すら苦しくなってくる。背骨が軋む。痛い。でも離してほしくない。
「……毎晩、そんな夢を」
押し殺したつぶやきに、ひどい羞恥が込み上げた。奏人は自分を軽蔑したんじゃないだろうか。普通ではない、倒錯した願望がある人間だと思ったんじゃないだろうか。
「か、奏人、ちがう。俺はそんなことしたくない」
「当たり前だ!」
いきなり声を荒らげられ、びくりと身体を離した。至近距離で目が合う。奏人は今まで見たことがないほど怖い顔をしていた。
「俺がどんな思いで兄さんから離れたと思ってるんだ。俺は兄さんのそばにいちゃいけないんだって、俺がそばにいたらろくなことにならないんだって」
「おまえだけが悪いんじゃない。俺だっておまえを──」
「そういう意味じゃない。最初からまちがってたんだ。俺は兄さんのそばにいちゃいけない人間だった」
奏人は泣きそうな顔で七緒を見つめる。
「……でも、もう無理だ」
奏人が顔を寄せてくる。切なさと怯えと不安と興奮。
それらすべてが入り混じった、ひどく切羽詰まった目の色だった。
「……奏人」
唇がふれた瞬間、水に落としたインクのように気持ちがにじんで広がった。違和感なくなじむ体温。どんな角度でくちづけようと、互いの唇はぴたりと密着した。
シャツの下から手が忍び込んでくる。唇と同じように手のひらも肌に密着し、七緒の形を覚え込むように腰から脇腹のラインを辿っていく。
「……っ」
くちづけは首筋へと移り、軽く吸われるだけで痺れるような波紋が広がる。手は脇腹を這い上がり、ラインにしたがって生まれた熱はまっすぐ下腹に落ちていく。足の中心でいきどまった熱が、腰全体をぐずぐずに蕩かせてしまう。
自分を芯からとかしてしまう感覚が怖い。これ以上進んだら戻れなくなる。
「……奏人、これ以上は」
わずかな抵抗。けれどソファに押し倒され、強引に衣服がはぎとられていく。
頭の中で赤色の警告音が鳴っている。なのにどこにも力が入らない。
本当は自分もこうなることを望んでいた。
毎晩夢の中で一方的に汚されながら、これが奏人ならと何度も思った。
「ずっと兄さんが好きだった」
胸の先にくちづけられ、びくりと大きく身体がはねた。濡れた舌先でわずかに嬲られただけで、そこは固くとがってしまう。毎晩男たちからの愛撫を受けて敏感になってしまった身体が厭わしかった。奏人はそれらを次々と上書きしていく。
初めてなのに、初めてではない。なのに夢よりもはるかに熱い。
現実と変わらないと思っていたけれど、奏人から施される行為はまったくちがう。
奏人が身体を下にずらしていく。すでに反応している性器に息がかかる。奏人の目に映っているだろう光景を想像すると全身が羞恥に灼けた。
「……あ、か、奏人」
先端ににじんだ蜜を吸われ、張り出した部分をゆっくりとふくまれていく。
敏感な場所を熱く濡れた舌で舐め転がされ、あとからあとから蜜がこぼれる。
快感に耐える中、固く閉じた背後に奏人の指がふれてくる。唾液のぬめりを借りて、やわやわとこねられるうちに、そこは待ちわびるような反応を見せはじめた。
指が入ってくる。一番によみがえったのは夢で味わった嫌悪感だった。
夢とはちがう。身体が自由に動くので、つい抵抗しそうになる。
でもこれは奏人だ。そう言い聞かせて耐えていると、不意打ちで全身が痺れた。
「うっ、あ……っ」
浅い場所で指を曲げられるたび、弱い電流に似た快感が爪先まで流れる。
性器の裏側あたりを強く刺激され、強烈な快感が沸き起こった。全身に汗が噴き出す。湧き上がる快楽は夢とは比較にならない。
「や、これ、や、め……っ」
後ろだけでも耐えがたいのに、性器への口淫も続いている。
呼吸がどんどん速くなる。みるみる限界が近づいてくる。
愛撫が一層激しさを増し、頭の芯まで灼けるような快感に性器が大きく爆ぜた。
放たれたものを、奏人はためらいなく飲み込んでいく。
射精のあとも、少しも熱が冷めない。それどころか、奏人の指を食んでいた場所はじくじくと疼きつづけ、さらなる快感を待ちわびている。毎夜のおぞましい夢で、そこは貫かれる快感を知ってしまっている。
七緒をラグに下ろし、奏人は薬が入っている棚からワセリンを取り出した。それを潤滑剤にして、熱く猛ったものを背後に当てがわれる。ぼんやりしていた頭が一気に冷めた。
「奏人、待……っ」
ここまできて、ふたたび背徳感と罪悪感がよみがえってくる。おじけづいて逃げる身体を、強い力で拘束された。
「……兄さんだけが、死ぬほど好きだ」
ひどく苦しそうな告白だった。抱きしめられ、身動きできないまま散々蕩かされた場所に圧がかかっていく。拓かれていく感覚にきつく目をつぶった。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細