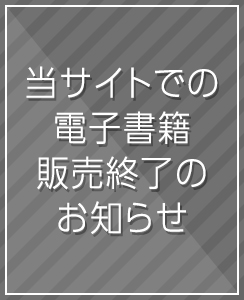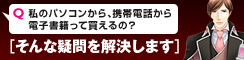死にたい病に効く薬
愛されてるって分かってきた?
幼い頃に双子の兄を亡くし、親の愛情を貰えず大人になった涼也。自己評価が低く、耐え難い自己嫌悪に陥る時がある。そんな時は行きずりの男に酷く抱かれて、擬似的な死を演出している。だが、その夜に出会った美貌の男・双樹は、願望とは真逆の甘い快楽で涼也を泣かせた。優しく包み込まれたようで心惹かれながらも、彼とは一夜限りのはずだった。なのに思わぬ再会をして……。
「なにを考えているの?」
囁くほどの声で言ったつもりが、誰もいない庭に双樹の声は思いがけないほど響いた。
涼也はびくっとしてこちらを向いた。
しかし、驚きの表情はすぐにふっと和らいだ。
「……どうして、また…現れちゃうんだろうな」
苦笑いする。
「ダメだった?」
「だって、元気な顔を見られてよかったなって噛み締めていたところだったんだよ。今度こそもう会うことはないだろうってね」
「何度でも会うさ。運命だって言ったじゃない」
「ただの偶然だってば」
「偶然をもたらすのが運命ってこと」
言い張る双樹に、涼也は溜息を吐いた。
「なかったことにしたほうがいいと思わない?」
「思わない。オレはきみを忘れられない」
「忘れて欲しいのに……」
伏し目になった涼也の前に立ち、双樹は涼也の頬に手を伸ばした──一撫で二撫でしたところで、涼也が顔を上げた。
しっとりと潤んだ瞳に誘われるようにして、双樹は涼也に口づけた。
触れただけで離れ、また視線を捉えた。
「きみだってオレを忘れてなかったくせに……さっき、ちょっとハグしただけなのに、全身で反応してたよね?」
「………」
「もう一回抱かせて」
「ダメだよ」
弱々しい拒絶だった。
だから、もう一度口づけをした。
「ダメって言ったじゃない……あぁ、ダメ…──」
涼也は手を突っ張ったが、もう容赦しなかった。
唇を割って歯列を潜り抜け、舌を絡ませた。逃げる舌を追い、吸い上げつつ、何度か唇の角度を変えた。
唾液が泡立ち、甘くなる……!
「……あ、あぁ」
涼也の口から熱っぽい溜息が漏れ、抵抗する気を無くしたのが分かった。
掬い上げるようにして、抱き寄せた。
スーツの布地は荒くて嵩張るし、全体に女性のような柔らかさはないのに、どうしてこれほどしっくりくるのだろう。
首筋に息を吹きかけるようにして、双樹は再び口説いた。
「……ね、抱かせて」
「………」
「一緒に気持ち良くなろう」
返事をしない涼也に焦れ、双樹は抱いている腕を緩めてその顔を覗き込んだ。
「いいよね?」
「……こ、今夜はダメだよ」
この期に及んで、まだつれないことを言う。
「どうして?」
「僕には連れがいるから」
「ああ、赤ワンピの社長さんか」
「彼女の部屋に行くって約束してるんだ」
涼也はアフターを匂わせたが、少し口調がきっぱりしすぎていた。
違う、と双樹は直感する。
「部屋に行って何するの? 添い寝?」
「そんな…聞くこと?」
気を悪くしたというよりは、下世話な問いを訝るような返しだった。
双樹は低く笑った。
「あの手の大きいおねーさんの相手は、涼也くんには荷が重いんじゃないかって思ってさ」
「そ、そんなことは…──」
声に動揺が入り交じる。
(そうか、やっぱり図星か。追い詰める気はなかったんだけど……)
再び腕に力を籠め、双樹は涼也を自分の身体にしっかりと引き寄せた。
「どっちにしろ、今夜は無理じゃない? 飲み過ぎてるし……何より、オレとこんなにくっついて、前に抱き合ったことを思い出してしまってるもんね」
一方の腕を滑らせ、背中から腰のカーブへ……そして、おもむろにぎゅっと臀部の肉を握った。
「!」
「……小さくて、引き締まってるよね」
「放して」
「抱かせてくれる?」
いやいやと首を横に振るのに、今度はその手を前へ。
涼也は全力で身体を引き離そうとする──が、許さない。双樹はまんまと涼也の足の間に膝を入れた。
そっと下から揺らし、探る。
「……や、やめて」
ほとんど泣き声だ。
「あぁ、堅くなってきたね……嬉しいな」
「……意地悪、しないでっ」
「どっちが意地悪なんだか。無視しようとしたり、話すことなんかもうないって言ったり」
「………」
「ね、抱かせて」
ややあって、涼也はこくんと頷いた。
双樹はそのつむじに口づけた。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細