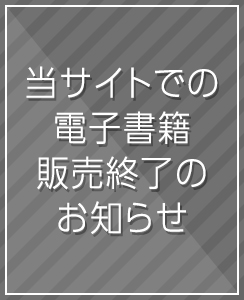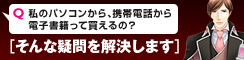地角の衆生
書籍紹介
一緒にいないと、寂しくて死んじゃう。
夜ごと仲間を探して啼いていた鵺は、人間に脚を射られてしまう。ところがその人間・寛慶は、痛みと怯えで泣きじゃくる鵺を見ると家へ連れ帰り、手当てをしてくれた。寛慶は鵺を厭わなかった。そばにいて、触れてくれる。ずっと欲しかった温もりが嬉しくて、鵺はこれからも寛慶と一緒にいたいと思う。そして、寛慶もまた癒えない寂しさを抱いていると知り、思わず彼を抱きしめて……。
立ち読み
「寛慶も、ひとりなの?」
まっすぐに投げた言葉に、男の瞳が寂しげな色を湛えた。
泣き出しそうにも見えて、唐突に胸が締め付けられる。
もしかしたら己はまた、寛慶を傷つけてしまったのかもしれない。
鵺が慰めるように頬をすり寄せると、寛慶ははっとしたような顔をした。
「どうした」
「ごめんなさい」
謝罪した鵺に、寛慶が笑う。
「突然どうした。なにを謝る」
「だって、寛慶が……なんか、痛そうな顔をするから」
重ねた鵺の言葉に、寛慶は唇を引き結んだ。
怒っているようではない。だが、どうすればいいのか思いつかず、その肌に触れた。いつか彼がしてくれたように、慰めになるだろうかと。
「ねえ、寛慶」
呼びかけに、寛慶がゆるりと首を傾げる。
「俺たちどっちもひとりなら、一緒にいたらどうかな」
同じ種類だから、仲間になるとは、愛してくれるとは限らない。
けれど、同じ種類じゃなくても、気にかけてくれるものもいる。そう言ってくれたのは寛慶だ。
だから人間と妖だけれど、寛慶と鵺は仲間にもなれるし、愛し愛されることだって、出来るのではないだろうか。
寛慶は、こんな姿の鵺を拒まないでいてくれた。
本当は殺されて遺骸を晒すはずだった鵺を、見逃してくれた。今もこうして、邪険にすることもせず、傍にいることを許してくれる。
それどころか、誰もが──迅雷でさえ滅多なことでは触れようとしなかった鵺に、躊躇なく触れてくれる。
その優しさに縋りたくなって、鵺はもう一度寛慶の手に頬を寄せた。
「一緒にいて、くれる?」
「……そうだな」
男は笑って、鵺の首に腕を回した。
寛慶が触れてくれたり、自分から抱きついたりすることはあっても、こんな風に顔を、体を密着させることはそれほど多くない。
散々接触をしていたくせに、慣れぬ距離感にひどく胸が騒ぐ。反射的に体を強張らせた鵺に、寛慶は怪訝そうな声をあげた。
「どうした?」
「なんでも、ない」
重みや、触れる体温の心地よさ、低く響く互いの心音に、鵺は覚えず笑みを零す。
──あたたかい。いい匂い。
頬が火照り、胸から湧き上がってくるあたたかなものに突き動かされ、笑いだしてしまいそうだった。
──どうしよう、嬉しい。嬉しい……!
同じ仲間が欲しいと、そう願っていた。
けれど本当は、ただこうして触れ合う相手がいるだけで十分だったのかもしれない。
少なくとも今はただ、寛慶と一緒にいたかった。
一際強く抱き返してくる腕が嬉しくて、鵺は寛慶の首筋に顔を埋める。
まっすぐに投げた言葉に、男の瞳が寂しげな色を湛えた。
泣き出しそうにも見えて、唐突に胸が締め付けられる。
もしかしたら己はまた、寛慶を傷つけてしまったのかもしれない。
鵺が慰めるように頬をすり寄せると、寛慶ははっとしたような顔をした。
「どうした」
「ごめんなさい」
謝罪した鵺に、寛慶が笑う。
「突然どうした。なにを謝る」
「だって、寛慶が……なんか、痛そうな顔をするから」
重ねた鵺の言葉に、寛慶は唇を引き結んだ。
怒っているようではない。だが、どうすればいいのか思いつかず、その肌に触れた。いつか彼がしてくれたように、慰めになるだろうかと。
「ねえ、寛慶」
呼びかけに、寛慶がゆるりと首を傾げる。
「俺たちどっちもひとりなら、一緒にいたらどうかな」
同じ種類だから、仲間になるとは、愛してくれるとは限らない。
けれど、同じ種類じゃなくても、気にかけてくれるものもいる。そう言ってくれたのは寛慶だ。
だから人間と妖だけれど、寛慶と鵺は仲間にもなれるし、愛し愛されることだって、出来るのではないだろうか。
寛慶は、こんな姿の鵺を拒まないでいてくれた。
本当は殺されて遺骸を晒すはずだった鵺を、見逃してくれた。今もこうして、邪険にすることもせず、傍にいることを許してくれる。
それどころか、誰もが──迅雷でさえ滅多なことでは触れようとしなかった鵺に、躊躇なく触れてくれる。
その優しさに縋りたくなって、鵺はもう一度寛慶の手に頬を寄せた。
「一緒にいて、くれる?」
「……そうだな」
男は笑って、鵺の首に腕を回した。
寛慶が触れてくれたり、自分から抱きついたりすることはあっても、こんな風に顔を、体を密着させることはそれほど多くない。
散々接触をしていたくせに、慣れぬ距離感にひどく胸が騒ぐ。反射的に体を強張らせた鵺に、寛慶は怪訝そうな声をあげた。
「どうした?」
「なんでも、ない」
重みや、触れる体温の心地よさ、低く響く互いの心音に、鵺は覚えず笑みを零す。
──あたたかい。いい匂い。
頬が火照り、胸から湧き上がってくるあたたかなものに突き動かされ、笑いだしてしまいそうだった。
──どうしよう、嬉しい。嬉しい……!
同じ仲間が欲しいと、そう願っていた。
けれど本当は、ただこうして触れ合う相手がいるだけで十分だったのかもしれない。
少なくとも今はただ、寛慶と一緒にいたかった。
一際強く抱き返してくる腕が嬉しくて、鵺は寛慶の首筋に顔を埋める。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細