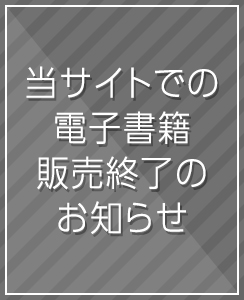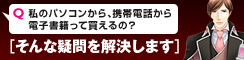神和ぎの我が手取らすも
書籍紹介
わたしは神和ぎ──贄なのです。
宗教団体に勤める馨は、「神和ぎ」として教祖を癒す役割を担っていた。務めを果たせなければ、教祖の側近・葛城に折檻される。身寄りのない馨を引き取ってくれた教祖への恩返し、そう思ってきたが、務めの度に心が打ちのめされるようだった。そんな時、取材に訪れた太田と出会う。なぜか馨に興味を示す彼に戸惑うが、あたたかな感情で包み込むようなその腕に、涙がこぼれて……。
立ち読み
「何か苦しいことがあるなら、話してくれないか? 力になれることがあるかもしれない。教団の顔としての君じゃなくて、普通の二十三歳としての不安や不満を感じている君が知りたいんだよ」
「違います。本当に、不満なんてないんです。わたしはそんなことを言える人間じゃないから……」
「馨くん……?」
大田に「君を知りたい」と言われるほどに、馨は自分というものがわからなくなっていく。これまで誰かに自分自身について問われたことがない。馨は教団の中にいて、常に「おまえはこうだ」と言われて育ってきたのだ。
教祖の言葉がすべてだった。葛城の命令が自分の成すべきことだった。もちろん、今もそう信じているからこうして大田の取材を受けて、この離れまで案内してきた。
「わたしは……?」
誰なんだろう。いきなり降って落ちてきたような疑問に、馨は大田がそばにいるにもかかわらずすっかり混乱していた。
「大丈夫かい?」
気がつけば大田があのときと同じくらい近くにいて、心配そうに馨の顔をのぞき込んでいる。なぜかわからないが、この人が自分のことを気にかけてくれているのはわかる。それが雑誌の編集者としての好奇心なのか、それとも人としての常識的な行為なのか、それさえも判断がつかない自分が不安だ。
(ど、どうしよう……)
このとき馨は泣き出してしまいそうになっていた。母親を亡くしたときに声と涙が涸れるほどに泣いた。あれ以来気持ちが弱くなって泣いたことはない。葛城に肉体的な苦しい責めを受けて流したのは、生理的な涙でしかなかった。
なのに、今は本当に心が弱くなっている。大田の顔を見上げるときっと目尻に溜まった涙がこぼれてしまう。だから、馨はひたすら俯いて小さく肩を震わせる。
「君はなんだか壊れてしまいそうだよ。どうすれば、君を守ってあげられるだろう……」
そんな言葉とともに大田の両手が馨の体を抱き締めたので、驚いて咄嗟に身を引こうとした。こんなところを誰かに見られたら大変なことになる。葛城の耳にでも入れば、また叱られる。
だが、ここは馨の家だ。母親亡きあとは、たった一人で暮らしている小さな住処だ。誰の目もここまでは届かない。そう思った途端、急に不思議な安堵感とともに大田の胸に頬を寄せてしまった。
(守ってくれる……? 彼が、なぜ……?)
昨日今日出会ったばかりの大田が、なぜ馨を守ろうとしてくれるのか? 自分は教団や教祖に守られているのではないのだろうか。彼と会うたび馨の頭の中は混乱するばかりだ。
そのとき、きちんと閉じきっていなかった雪見窓からわずかに風が入ってきた。秋の気配のする少しひんやりとした風だ。その風から馨を庇うように大田が立っている。抱き締められながら感じていたのは、これまで知らなかった人肌の温もり。
教祖や葛城の腕の中とは違う。このどこまでも優しい感覚が馨の気持ちを包み込むようだった。
「違います。本当に、不満なんてないんです。わたしはそんなことを言える人間じゃないから……」
「馨くん……?」
大田に「君を知りたい」と言われるほどに、馨は自分というものがわからなくなっていく。これまで誰かに自分自身について問われたことがない。馨は教団の中にいて、常に「おまえはこうだ」と言われて育ってきたのだ。
教祖の言葉がすべてだった。葛城の命令が自分の成すべきことだった。もちろん、今もそう信じているからこうして大田の取材を受けて、この離れまで案内してきた。
「わたしは……?」
誰なんだろう。いきなり降って落ちてきたような疑問に、馨は大田がそばにいるにもかかわらずすっかり混乱していた。
「大丈夫かい?」
気がつけば大田があのときと同じくらい近くにいて、心配そうに馨の顔をのぞき込んでいる。なぜかわからないが、この人が自分のことを気にかけてくれているのはわかる。それが雑誌の編集者としての好奇心なのか、それとも人としての常識的な行為なのか、それさえも判断がつかない自分が不安だ。
(ど、どうしよう……)
このとき馨は泣き出してしまいそうになっていた。母親を亡くしたときに声と涙が涸れるほどに泣いた。あれ以来気持ちが弱くなって泣いたことはない。葛城に肉体的な苦しい責めを受けて流したのは、生理的な涙でしかなかった。
なのに、今は本当に心が弱くなっている。大田の顔を見上げるときっと目尻に溜まった涙がこぼれてしまう。だから、馨はひたすら俯いて小さく肩を震わせる。
「君はなんだか壊れてしまいそうだよ。どうすれば、君を守ってあげられるだろう……」
そんな言葉とともに大田の両手が馨の体を抱き締めたので、驚いて咄嗟に身を引こうとした。こんなところを誰かに見られたら大変なことになる。葛城の耳にでも入れば、また叱られる。
だが、ここは馨の家だ。母親亡きあとは、たった一人で暮らしている小さな住処だ。誰の目もここまでは届かない。そう思った途端、急に不思議な安堵感とともに大田の胸に頬を寄せてしまった。
(守ってくれる……? 彼が、なぜ……?)
昨日今日出会ったばかりの大田が、なぜ馨を守ろうとしてくれるのか? 自分は教団や教祖に守られているのではないのだろうか。彼と会うたび馨の頭の中は混乱するばかりだ。
そのとき、きちんと閉じきっていなかった雪見窓からわずかに風が入ってきた。秋の気配のする少しひんやりとした風だ。その風から馨を庇うように大田が立っている。抱き締められながら感じていたのは、これまで知らなかった人肌の温もり。
教祖や葛城の腕の中とは違う。このどこまでも優しい感覚が馨の気持ちを包み込むようだった。
おすすめの関連本・電子書籍
- プラチナ文庫
- 書籍詳細