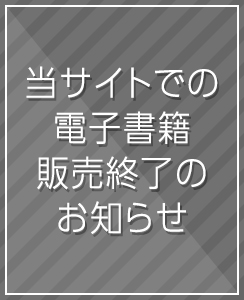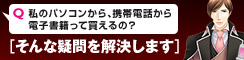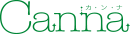私の愛しいお人形
僕は、恋人にはなれない仕様です──。
白金の髪を持つ茶問屋の跡継ぎ・冬伍は、友人の会社の従業員である千春に心惹かれた。
だが彼はバイオノイドで、前任者が行方不明になったため自分は“二人目の僕”だと言う。
人との差異を受け入れ、哀しいまでに人に尽くそうとする千春。
冬伍はそんな彼に共感と、いっそうの愛しさを覚える。
けれど前任者の行方を追ううち、危機が迫り──「お願い。僕が壊れても泣かないで」
「前の君のことは残念だった」
青柳の声が哀切に響く。なんとなく言えずにいた結末を知ったのだと気づき、千春は目を伏せた。
「誰かに何か聞いたんですか?」
「天晴が教えてくれた。特別なランチを食べなければ、君たちは三日しか保たないと」
「そう、ですか……」
その通りだし、天晴に悪気はないのはわかっているが、青柳には知られたくなかった。千春は青柳の前では何ら瑕疵のない存在でいたかったのだ。
「レーションがギリギリの数しか支給されないのは、逃亡を防ぐためか?」
淡々と問われ、千春は弾かれたように顔を上げた。
「違います。──いえ、それもあるのかもしれませんが、それ以上にカンパニーの偉い人たちは僕たちの生命の秘密が外に漏れるのを恐れているんです。僕たちみたいな存在はまだ他にいないでしょう? もし攫っても、三日で死ぬと同時に変質が始まってしまえば得られるものはほとんどありません。余分なレーションを持っていなければ再現されてしまうリスクもなくなります。だから、これでいいんです」
「私にはそんな風には思えない。カンパニーは君たちの命を軽視している」
壁に寄り掛かり腕を胸の前で組んだ青柳の姿はどこか厳粛なものを漂わせていた。何かを断罪しようとしている高貴な存在のように。
「仕方ないです。僕は──」
「人間ではないんですからは聞き飽きた」
ふっと溜息をつくと、青柳は壁を離れた。またしても抱き締められてしまう。誰に対しても氷雪のように冷たいのに二人きりになると蜂蜜並みに甘く豹変するのにはもう慣れたつもりでいたけれど、今日は特に甘えただ。青柳の方がずっと体格がいいのに、なぜか小さな子供に縋られているみたい。
黙ってされるままになっていようかと思ったりもしたけれど、それも変な気がして、千春は躊躇いがちに唇を開く。
「あの……」
「何だ?」
「どうしてこんな……その…………ぎゅっとするんです、か……?」
青柳の返答は簡潔だ。
「そうしたいからだ。厭か?」
千春は返答に詰まる。厭ではない。厭ではないのだが……困る。
「僕をぬいぐるみと間違えていませんか……?」
「ぬいぐるみか。それはいい。人形ならいつだって傍に置けるからな」
髪を掻き分けるようにして、高い鼻梁が頭のてっぺんに擦りつけられるのを感じた。
「君を私の手元に置くことはできないだろうか」
どくりと心臓が鳴る。なんだかプロポーズされているような気分だ。
「僕は棗さまと契約していますから」
「もし棗が契約の解除に応じたら?」
可能だ、と言ったらこの人は友人を説得しようとするのだろうか。だが、そう簡単に運びそうにないことを千春は知っていた。
「もし棗さまが口添えしてくださったとしても、僕が冬伍さんの下に派遣してもらえるとは思えません。カンパニーは恐れているんです。オートマタに悪評が立つことを。たとえば僕が冬伍さんを誑かしたとか」
「本当に?」
「はい。すでに数件そういう求めがあって、人間に気を持たせるような言動を取るなというお達しが来てます」
欲しいと言われるのはとても嬉しいことだけれど、千春たちはオートマタだ。誰よりも立場が低い。その人の親やその人を手に入れたがっている人にクレームを入れられればカンパニーは対処せざるをえない。既に処分された個体もあるという話はチューターからこっそりと教えられた。
──僕たちには、いくらでも代わりがいるんだ。
記憶の欠落がなければ、人間は入れ替わっていることに気づかない。前の自分の記憶は自分自身の記憶とは違ってどこか遠く、昔見た映画のよう。前の自分がその人に恋していたとしてもその感情は他人事だ。前の自分がそのせいで廃棄されたと知っているオートマタはまずカンパニーの要望通りに行動する。突然冷たくなった恋人に驚き掻き口説かれたとしても心が揺れることはない。
カンパニーがオートマタの気持ちより保身を優先する理屈はわかる。わかるけれど、彼らのことを考えるととても哀しい気分になる。
「だが、君をこのままにはしておけない」
「ありがとうございます。僕のことを思ってくださって、とても嬉しいです。でも、僕はもう、いつ死んでもいいって思うくらい幸せなんですよ?」
「……不吉なことを言うんじゃない」
怒ったような声と共に顎をすくい上げられる。唇を塞がれて、千春はそっと目を伏せた。
青柳さまにキスされるの、好き。すごく幸せな気持ちになる。まるでお伽噺の主人公になったよう。あるいは雲の上をふわふわ漂う夢を見ているよう。
しばらく後、優しいキスをほどいた青柳の顔は何とも言えず哀しげだった。
だから千春はふんわりと微笑んでみせる。
「さっき、玄関で冬伍さんを迎えた時、ちょっとびっくりしました。冬伍さん、チューターと僕の見分けがついているんですか?」
青柳は傲然と嘯いた。
「当然だろう?」
そうか。当然なのか。
嬉しい気持ちに胸の裡を満たされる。
「僕たち、何もかも同じだと思うんですけど」
「性格の違いが表情に出ている。チューターは厭世的で、君は無垢だ」
無垢。
かーっと頬が熱くなる。千春は青柳の胸元に顔を埋めた。
「もー、冬伍さんはどうしていつもそういうことを言うんですか……」
褒められると嬉しいけれど、それ以上に恥ずかしくていたたまれない。だが、青柳にはそんな千春の気持ちなど理解できないらしい。きょとんとした。
「何を怒っている」
「僕は冬伍さんが言うような存在じゃ全然ないんです。嬉しがらせるのは止めてください。あなたのこと、もっと好きになってしまう……」
好きになればなるほどさよならがつらくなるのに。
「なればいい」
照れ隠しに取り乱す千春に、青柳はあっさりと、偉そうに言う。
「むしろ、なれ」
優しい指が髪を梳く。ちょっと死んじゃいそうなくらい、幸せだ。
──今だけで、いいんだ……。
いちゃいちゃしていると、青柳の上着の中で震えるものがあった。小さく舌打ちし、青柳が内ポケットから携帯を取り出す。表示されたメッセージに目を通した青柳が渋面となった。
「──土曜日の午前中に仕事が入った……」
「えっ」
折角チューターに服を選んでもらおうとしていたのに、デートは中止になってしまうのだろうか。
だが、青柳は当たり前のように続けた。
「どうする? 後で向こうで合流してもいいが、一緒に来るか? 一、二時間待って貰うことになるが」
「……一緒に行きたいです」
おずおずとねだってみると、今度は額にくちづけられた。
「日帰りではあまりゆっくりできないな……泊まりはやはり無理か?」
泊まり……夜を一緒に過ごす……? チューターがさっきくれたポーチがぽんと頭に思い浮かび、千春はどうにかなってしまいそうな気分になった。
「事前に申請すれば、二食分までレーションを貰えます」
「そうか。では宿も押さえておこう。……楽しみだ」
青柳が喋ると息が膚をくすぐり──千春は震えた。この人が喜んでくれるなら、何だってやる気だった。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細