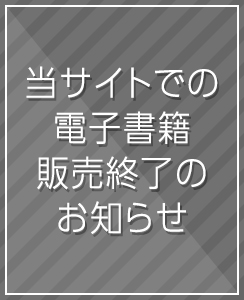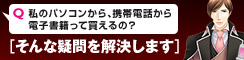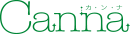天水桃綺譚
僕を、食べてくださいませんか?
桃農家の亨が見つけた、金色の芳しい桃。それは、天から落ちた桃の精だった。金髪の美しい少年に変じモモと名付けられた彼は、天真爛漫に下界での暮らしを楽しむ。ぎこちなくも不器用な優しさで見守る亨と、純真なモモはやがて想いを寄り添わせていくが、それは許されぬ恋だった──。その後のふたりに加え、白虎さまに恋慕する、未熟な桃の精・コモモの切ない恋物語も書き下ろし。
「モモ、どうしたんだ。具合が悪いなら早く医者に行こう、な?」
抱きしめたまま持ち上げようとしたが、
「お医者には行きません!」
モモは全身に力を込め、頑として立ち上がらない。
「じゃあ、モモはどうしたいんだ」
問いかけても、モモはうなだれたまま答えない。
「……モモ」
ひどく苦しくて、亨は目を閉じた。こんな切ない恋を前にして、それでも大人でいなくてはいけないことがつらい。わがままな子供のように、モモが好きだと泣き喚きたい。心のまま、モモがほしいと駄々をこねたい。
「……亨さん」
名を呼ばれ、顔を上げるとモモが手を伸ばしてきた。唇を寄せられ、触れる寸前かわせたことは奇跡だった。モモが傷ついた目でこちらを見る。
「……どうしてですか? 昨夜と同じなのに」
悲しそうに問われ、モモがなにを望んでいるのかようやく理解した。
「モモ、昨日のことは違うんだ」
「……違う?」
焦りと自己嫌悪が込み上げてくる。
「あ、あれは俺とモモがするもんじゃない。昨日は俺がどうかしてたんだ。あんなことは二度としない。すまなかった。この通りだ」
くちづけの意味すら知らないモモの無垢さや無知さにつけ込んで、それ以上のことに及ぶのは簡単だ。けれど自分がほしいのはそんなものではなかった。
「二度としないのですか?」
「絶対にしない。誓う」
頭を下げる亨の耳に、そうですねとつぶやきが聞こえた。
「……接吻は愛しい御方としかしないものだと、僕も知ってます」
はじかれたように顔を上げた。
「ちょうど僕が生った木の下が、白虎さまが愛しい御方とお逢いになられる場所だったのです。白虎さまは神仙さまの中でも特に見目麗しく、恋多く、夜毎女仙さまとお話をされたり、唇を重ねられたり、とても楽しそうでした」
頭が混乱した。子供の目の前で父親が妻や他の女とくちづけるなんて考えられない。それは本当に父親の話なのかと、初めて疑念が湧いた。
「でも、なぜ唇を重ねるのかがわからなくて、僕、白虎さまにお尋ねしたことがあります。白虎さまは笑いながら教えてくださいました」
モモは淡々と話を続ける。
「あれは接吻というものだと。愛しく想う相手に触れたく、胸が締めつけられ、そうせずにはいられなくなるものなのだと。それが恋情という想いだと」
亨は渾身の力で拳をにぎり込んだ。これほど恥ずかしく、居たたまれない思いをしたのは初めてだった。モモは亨の恥知らずな行為の意味を知っていた。
「だから、僕、嬉しかったのです」
モモがぽつんと言った。
「亨さんに接吻されたとき、白虎さまの言葉を思い出しました。だとしたら、亨さんは僕を愛しく想ってくださっていると、僕、とても嬉しかったんです」
思ってもみなかったモモの言葉に、にぎり込んだ拳の中で汗が噴き出す。
「でも、そうではありませんでした。亨さんは僕を子供みたいにかわいがってくれているだけで、それで充分なのに悲しく、僕、わがままを言ってしまいました」
「モモ、俺は──」
「いいんです。ごめんなさい」
笑顔で言葉を遮られた。
「僕、天の桃です。天の桃は良い子なので、わがままは言いません」
モモはぐすっと洟をすすった。
「それに桃は……恋なんてしませんから」
笑いながらぽろぽろと涙をこぼすモモを、亨は思い切り抱きしめた。
「お、俺はモモに恋している」
ほっそりとした身体を一層きつく抱きしめた。
「……亨さん?」
「俺にはモモしかいない」
こんなにたくさんの人がいる中で、どうしてモモなのだろう。
誰からも祝福されない。なのにどうしてモモでないと駄目なのだろう。
誰かに説明する言葉はなく、その必要もなく、ただそうせずにはいられない心があるだけだ。親も夫も世間もなにもかもを振り切って、愛しい恋人の胸に飛び込んでいった妻の気持ちが、初めてわかった気がする。
「……本当ですか?」
震える声で問われ、大きくうなずいた。
「ああ、誰よりもモモを愛している」
涙で濡れた目元を愛しむように幾度もくちづけた。
口の中に瑞々しい果実の甘みが広がる。頬に流れ落ちる甘い雫を辿り、ゆっくりと唇を重ねた。軽く触れ合うだけのつもりが、くちづけはどんどん深くなってしまう。
すんなりとした腕が首に回る。抱きしめられる。
こんな単純で深い喜びを、今まで知らなかった。
くちづけを交わすたび、互いの間にある空気の隙間が消えていく。ぴたりと重なって、逃げ場を失った体温が内側に熱を送り込んでくる。夢中で細い鎖骨を辿り、指先をモモのシャツのボタンにかけ、ふと現実感が蘇った。
「亨さん?」
停滞した流れにモモが目を開ける。これ以上のことをしてもいいのだろうか。動けない亨に、モモがゆったりとくちづけてくる。
「亨さん、僕、とても幸せです」
「モモ」
「本当に幸せです」
淡い闇に溶けそうなつぶやきだった。薄い手のひらが亨のうなじをくすぐり、髪に優しく触れてくる。髪の流れに逆らうように梳かれ、肌が甘く粟立った。
「白虎さまが、いつも愛しい御方とこのようにされておられました。なぜそんなことをするのか、今、わかりました。とても幸せで、もう言葉がありません」
モモがうっとりと目を閉じる。息苦しいほどの幸福感がせり上がってきて、愛しいと想う心以外のものを、甘く柔らかく押し出してしまった。
「俺も幸せだ」
かみしめるようにつぶやいた。
「自分がこんな気持ちになれるなんて信じられない」
こんなふうに気持ちを言葉にしていることも信じられない。すべてモモのおかげだ。モモと向かい合うと、固く結ばれていた帯のように心をほどかれる。
飽和状態だった愛おしさが、次々とはじけていく。
余計なことはもうなにも考えられず、今この時間に没頭した。
障子越しに差し込む月明かりに、モモの輪郭が仄白く浮かび上がる。
手のひらと唇で幾層にも愛撫を重ねて、互いの肌の継ぎ目さえわからなくなったころ、時間をかけて、ゆっくりとつながった。今にも窒息しそうな、気の遠くなるような悦楽に一気に高みまで引き摺り上げられる。
今すぐ果ててしまいたい。
けれど、この時間を少しでも長くわかちあっていたい。
真逆の望みに煽られ、室内にむせ返るような果実の香りが満ちていく。濃密なそれは障子の隙間から洩れ出し、月の輝く夜空に漂い出していく。
──見つけたぞ。
のぼせた意識の隙間を縫うように、鈴の音色のような声が聞こえた気がした。奇妙な気配を感じ、ふと現実に引き戻される。しかしそれも束の間、果実の香りと熱の立ち込める室内から、ひっそりと風は気配を消した。
- プラチナ文庫
- 書籍詳細